シンポジウム動画配信
28日のシンポジウム動画配信しています http//www.ogunigawa.org どうぞご覧ください。appleのQuickTime映像ですので、winの方はappleのページからquickTimeをダウンロードの後、ごらんください。
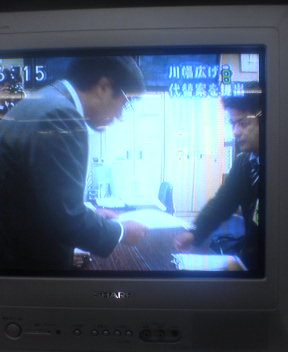

代替案提出
本日 先日のシンポジウムをふまえ 代替案を提出。 報道陣たくさん ぜひとも 6時台のニュースのチェックを!ビデオ録画 お願い!
小国川の真の治水を求めて
昨日のシンポジウム。「小国川の真の治水を求めて」には、200名以上の皆さんにお集まりいただきました。 おいで頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
今朝の山形新聞に以下のように記事が掲載されました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民主・菅氏ら招き最上小国川の治水や公共事業考えるシンポ
公共事業の在り方などについて意見を交わしたシンポジウム=新庄市民プラザ 最上小国川の治水対策として県が最上町に建設を計画している穴あきダムに反対する市民団体「最上小国川の真の治水を考える会」主催のシンポジウムが28日、新庄市民プラザで開かれた。菅直人民主党代表代行らが公共事業の在り方などについて述べた。
ダム建設に反対する小国川漁協の関係者など約200人が参加した。最初に今本博健京都大名誉教授と大熊孝新潟大教授、アウトドアライターの天野礼子氏が講演。引き続き天野氏をコーディネーターに、菅代表代行と五十嵐敬喜法政大教授が「本当に必要な公共事業を行うために」と題してパネルディスカッションを行った。
菅代表代行は「役所は金を使えば使うほど権限が強くなり、『いい物を安く』という考え方はない。国は年間10兆円ほどの無駄遣いをしており、公共事業はその象徴。日本の財政再建のスタートはこの改善しかないと考えている。市民、県民が税金を何に使うべきかしっかり考え、声を出して行動することが大切。そうすれば大きく構造は変わる」と述べた。五十嵐教授は「安倍政権のスローガンは『美しい国へ』。穴あきダムを造るよりも赤倉温泉街の活性化に投資するのが美しい国の姿ではないか。ぜひ政策を転換してほしい」などと語った。
最後に、河川掘削・拡幅などによる治水法を記した同会と今本名誉教授、大熊、五十嵐両教授、天野氏の連名による代替プラン「最上小国川真の治水案」を公表した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上山形新聞061029朝刊2面
今回、代替えプランとして発表したものは以下。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「穴あきダム」に依らない
最上小国川“真の治水”案 06.10.28
今本博健
大熊 孝
五十嵐敬喜
天野礼子
最上・小国川の真の治水を考える会
これまでの「旧来型の治水」は、一定規模以下の洪水を対象とし、河道改修やダムによって洪水を河道に封じ込め、水害を発生させないことを目標にしてきた。
私たちが21世紀にかなえたい“真の治水”は、「いかなる大洪水があろうとも少なくとも人命に及ぶような壊滅的な被害だけは避けるようにする」もので、しかも、河川環境に重大な影響を生じさせず、数十年に1度の洪水のときばかりでなく日常の生活にも役立つ治水方式である。
具体的には、河川対応と、流域対応による治水法を併用することとする。
1) 本来は河道であるところに建物が建ってしまっている。赤倉温泉地域の一 部を、河川掘削や拡幅、引き堤などで河道の流下能力を拡大させる。
2) 赤倉温泉下流域を「遊水地指定」し、洪水被害が生じたときには、「すべての被害」を補償する。
3)流域上流部の森林の、手入れがなされていない放置人工林等を間伐するなど、森林での保水能力を高める。
4)土地利用の規制・建物の耐水化・道路などの利用方法の2線堤化などによって、氾濫した場合の被害を少なくしていくことを考慮する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
記者、会場からの質問の中で、田辺省二県議会議員から、これ案を承認する旨のご意見を頂戴したり、様々な質疑がおこなわれた。
前の方にすわり、この提案に対して質問をして、菅直人氏らの対談の時に私語多数を天野氏に指摘されていた輩たちは、後に国土交通省の方々との事でした。マナーつうものを知らない輩でしたね。
いずれにしてもとても中身の濃いシンポジウムになりました。関係者各位、感謝申し上げます。また、私自身、凡ミスだらけの至らぬ事務局司会進行。大変失礼いたしました。
当日、うまく放映が叶わなかった最上小国川の映像は以下、アップデートしました。どうぞご覧ください。
http://homepage.mac.com/stern8/iMovieTheater21.html
とにかく、昨日のシンポを大きな布石とし、今後の運動に活かしていきましょう。
まだまだ、議論もこれからアクションもこれから、みんなで動き出しましょう。
山形に残る、一本の清流を救おう! そこから真に美しい国づくりははじまる!
wiloffermans 上田純子 のコンサート
昨日のウィルオッフェスマンズと上田純子のフルートと薩摩琵琶のコンサート。大松庵でおこなわれた。大松庵の日本家屋と薩摩琵琶、尺八の代表曲を奏でるフルート。響きは最高だった。
特に、芭蕉の出羽三山3句を歌い上げた出羽三山は圧巻。
次の日は三瀬保育園で子供達に琵琶の演奏、子供達に歌をつくらせ、琵琶にあわせてみんなで歌うワークショップ。そして壇ノ浦。などを披露。
実にすばらしかった。来年の来日まで、もっと多くの方とふれあえる企画を進めたい。
中越大震災から2年。
中越大震災から2年。
現地の方やボランティア仲間から連絡があり、小千谷、塩谷で合流を直前まで考えていたのだけれど、どたばたしていて行けずじまい。
5時56分。黙祷。
塩谷の皆様にファックスす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小千谷市
塩谷の皆様
直前までうかがう予定にしておりましたが、どうしても鶴岡を離れることができず、参上することができません。申し訳ありません。
2年前のあの日、天に召された、塩谷のお子さん達をはじめ、67名の方々に深く哀悼の意をささげます。
2年前の10月25日。避難所の小千谷高校で、みなさんにサッカーゴールで屋根をつくっていただいて、元気鍋を囲んだ事。当初から、ものすごい団結力を見せてくださった皆さんにお会いできた瞬間を私は忘れることができません。
そして元気村に集う若者達を快く受け入れてくださり、一緒に新しい文化をつくることができたこと。本当に感謝しております。
あの時から生まれた絆は、私たちにとっても大きなパワーの源泉。
これからも、皆さんを親戚のように慕い、塩谷を第二の故郷として通い続ける人はたくさんいることでしょう。
私も、今度ゆっくりと訪れさせて頂ければと存じます。
2006年10月23日、午後5時56分。残念ながら、また今年も鶴岡にて、
ご冥福と皆様のご多幸をお祈りさせていただきます。
真の復興にむけて、絆を深め、一歩一歩、歩んでいきましょう。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NHKの福祉番組の生放送を見ていたら、被災民家の建ておこしプロジェクトに邁進する新潟の建築家、長谷川さんがでていた。震災の3ヶ月後ぐらいに、「いきなり解体するのではなくできるだけ建ておこそう」と長谷川さんをはじめとする、思いをもった建築家や技術者が集まり、仮設住宅のセンターで「元気村の建ておこし」相談会」を開いたのがきっかけだった。よかった。山古志などでも順調に広がりを見せている。
それと、昨日にこんなメールがはいった。
Fです。
先週、朝日新聞の夕刊に「震災地から」という特集が連載されて
いたのをご覧になりましたか?
20日の金曜日は星野剛さんのお話で、仮設住宅に住んでいた頃の
楽しかった思い出として私の路上演奏会と、それに続いて始まった
路上での宴会(青空酒場)のことが書かれていました。
それがとても嬉しかったので星野さんのブログに書き込みをすると、
「あの演奏は仮設での一番楽しかった思い出だから朝日の記者に
話した」とメールをいただきました。
趣味で続けてきたフルート演奏でボランティアに行っても「自分の
好きなことをやってきただけだ」と言われても仕方なく、忸怩たる
ものがありましたが、これで本当に吹っ切れました。
星野さんには「また塩谷で演奏して欲しい」と言われました。
お堂の修復工事の準備をお手伝いさせていただいた福生寺も
懐かしく、修復が完了したらお堂で演奏させてもらいたいなどと
考えてもいました。
来年の春くらいには行きたいと思っています。ーーーーーーー
避難所で寝床になっていた小千谷高校の体育館で、はじめてフルートの生演奏を披露してくれたFさんからのメールだった。
2年。まだ5千人以上の方が仮設住宅にいる。山にもどるのがいいか、町場におりるのがいいか、迷いも続くかもしれない。塩谷地区では、ボランティアで集まった人たちや山を下りた住民がいつでも戻ってこれるよう。また、絆を深めることができるよう、芒種庵という拠点をつくった。11月4日には開所式と聞いているので、ぜひこの機会に訪れたいと思っている。
動けば変わる。つながる。元気になる。 このエネルギーの循環の中で、生まれた新しい文化を もっともっと!
僕も、エネルギー再充電。なんとかがんばっていこう!
という明日、これも神戸の仮説住宅での慰問コンサートをきっかけに知り合ったウイルオッフェスマンズと上田純子さんの薩摩琵琶とフルートのコンサートが鶴岡市内 大松庵でおこなわれる。すごい演奏なのでぜひお聞きのがしなく。問い合わせ 大松庵http://r.tabelog.com/yamagata/rstdtl/6000023/
うれしい記事 緩速濾過
10/20 水源切り替えデイにふさわしい記事が届いた。—————————
朝日新聞 長野版より
よみがえる旧式浄水場 須坂市が復活へ
2006年10月20日
80年前の大正末期に建設され、取り壊しを免れていた浄水場を、須坂市が「現役復帰」させる検討に入った。人口減などで水の需要も減り、新型浄水場の運営コストが重荷になってきた。しかも「旧式」は微生物の力を借りて水の臭みなどを取り除くことから、薬品を使う新型浄水場より「安くておいしい水」が期待できるという。昔の浄水施設の復活は全国的にも珍しく、財政難の地方自治体による「妙手」としても注目を集めそうだ。(浜田陽太郎)
復活するのは1926(大正15)年に完成した「坂田浄水場」。底に砂を敷き詰めた濾過(ろ・か)池に、市内を流れる灰野川の伏流水を引き込み、砂の中に生息する微生物などの働きで汚れを分解する。これは「緩速濾過」と呼ばれる方法で、1日あたり3400立方メートルを処理する能力があった。
急速な人口増が続くことを見込んで、市も約27億6千万円を負担した県の豊丘ダムが完成したのに伴い、1日9500立方メートルの処理能力を持つ最新式の「塩野浄水場」(事業費28億円)が96年に稼働。「坂田浄水場」は10年間、使用を休止していた。
だが人口は、冬季オリンピックのあった98年の約5万4800人をピークに、05年までに1100人以上減った。96年に4万2千立方メートルと設定した1日当たりの計画給水量も、04年には3万2600立方メートルに下方修正された。「塩野」1個分の需要が減った計算だ。
「塩野」では年間、ポンプで水をくみ上げるだけで電気代が700万円、濁りを沈殿させる「急速濾過」に使う薬品代に290万円、沈殿した泥を産廃処理するのに120万円かかる。さらに今年度予算では泥を集める機械の修理費に420万円も計上。税収が減っている市にとって軽い負担ではない。
一方、「坂田」はこうした運営費がほとんどかからず、現役復帰によって水道料金引き下げの期待も出てくる。浄水場すべてが緩速濾過方式の上田市の場合、1立方メートル当たりの供給単価は須坂市に比べて30円以上安いという。三木正夫市長は「人口が減少する状況では、費用対効果を考えるべきだ」と話す。
「坂田」が稼働を始めれば、「塩野」はトラブルがあった場合の「バックアップ用として維持することも選択肢」(市水道局)という。水道行政を所管する厚生労働省は「急速濾過の施設を休止し、緩速濾過を復活させる例は聞いたことがない」(水道課)としている。
市は、緩速濾過(生物浄化法)の第一人者である中本信忠・信大教授に依頼し、「復活」に必要な作業の調査に乗り出す。中本教授は「財政難に直面した市が、業者任せにせず自ら考えて、緩速濾過の良さに気づいた意義は大きい。こうした自治体は今後、増えていくのではないか」と評価している。
坂田浄水場の開設80年周年を記念し、市は20日午後2時から、市シルキーホールで中本教授の講演会などを開き、緩速濾過の意義などを市民に伝えることにしている。
————————–
この記事に登場している中本先生は、2003年の鶴岡での水郷水都全国会議でおいでいただいている。塩素は毒。緩速濾過や地下水の水は安くておいしい。微生物の濾過によって安定した水質になる。真摯に古くて新しい技術 緩速濾過の浄水場について力説する先生。高崎の歴史ある濾過池にもご案内いただいた。
須坂市のこの取り組みのようなことこそ、今、最も大事なことだと思う。国の言い分を鵜呑みにして、高コストでまずい水と住民に批判されるより、本当に知恵を絞って安くておいしい水を提供する方が絶対にいい。低廉で良質な水を提供するのは水道法で決められた水道事業者の責務なのだ。ところが今はそうなっていない。
ダム利権。水道浄水場利権。などなどなどにがんじがらめになっているのだ。
中本先生にももっともっと活躍してもらいたいものだ。僕も地下水や微生物浄化の復権を脱ダムとともに唱えていきたい。
10.20 鶴岡水源切り替えから5年。
10月20日。この日は、忘れもしない5年前、鶴岡の水道水源が地下水100%の
水道水から、月山ダムの水に切り替えられたその日。
5年前というと9月11日に同時多発テロが起きて世界が変わったといわれて
いるけれど、鶴岡の市民の暮らしは、実は5年前の10月20日に大きく変わっ
ているのではないでしょうか。おいしくて、冬ぬくもりがあって夏冷たい地下水
100%の水道水。食文化を支える大きな要素が、明らかに変化しました。
今はそれを、わざわざ水道料金の100倍もの値段の地下水販売所や、
1000倍もの値段のついたペットボトルを買い求めないと当時の水質の水を求
めることはできません。
そして、切り替えにともなってこの8年間で3度段階的に水道料金は引き上げら
れ、1.85倍と、切り替え以前の役2倍もの高額な水道料金になっているので
す。県から買う契約水量は72000トンで、現状5万トン足らずで減り続けて
いる現現状でみれば、あまりに過大であり、私たちは使わない水の分のお金まで
水道料金に上乗せさせられているという計算になります。
改めて提示しますが、山形県というのは、宮城県と並んで全国で最も水道料金
が高い県だっていうことをご存じでしょうか。全国の水道料金の格差は約9倍。
少ない人口のところで、ダムなどの巨大開発をして水源を確保し、広域水道など
に頼った水道にしたところで、軒並み、水道料金が高額になり、おおきな矛盾を
抱えることになるということであります。
もう、わざわざダムをつくって水道水源を確保しなくても、水は足りている。こ
れは、先日八つ場ダムの大集会もあったようですが、どこも同様です。
利水目的のダムというのは存在理由をほぼ失っています。
今、取り組んでいる、最上川の支流、最上小国川につくられようとしているダ
ムは、一番はじめの計画では水源を確保するための多目的ダムから構想がはじ
まっています。しかし、利水目的がほぼ失われたために途中から治水専用の目的
になっています。
全国のこうした事情を踏まえ、国土交通省が考え出したのが「穴あきダム」で
す。ダム提体の底に穴を設け、通常は川がそのまま流れ洪水時は一定量貯まると
いったものです。国や県の説明というのは、穴あきダムであれば、河川生態系に
もほとんど影響を与えないという説明です。
しかし、本当にそうでしょうか?
詳しいデータも未だ全く示されていません。
多くの川やダムを知る人たちは、ダム工事で川に手を入れた瞬間に川の環境が大
きく変わってくることを知っています。鮎の数がダム事業の前後で変化すること
をごまかそうと、ダム事業の直前の河川の調査を甘くして、そしてダム事業の後
に鮎の放流を激増させる。こうしたこともまかり通ってきました。
まさに、川を殺し続けてきたのがダム事業です。穴あきダムはどうかというと
今本先生は「穴あきダムでも自然環境に重大な負の影響が及ぶおそれがある」と
指摘しています。
いずれにしても県、国から、これまでの実例を元にした環境影響についての
データは全く示されていません。どんな影響があるのか、さっぱりわからない。
結局は、この「小国川が実験台になる」ということではないでしょうか。
清流最上小国川については、私は、まさに日本全国に誇れる、いってみれば世
界中に誇れる川だと思っています。天野礼子氏は、「日本の名河川を歩くという
著書」の中でこの川を日本で第二の名河川と称しました。先日、四国の清流、四
万十川をベースにしている鮎釣り氏が小国川を訪れましたが、「四万十の数倍、
この川はすごい」と絶賛していきました。その方のつてで、四国からまた、つり
師が訪れているとうかがっています。
つり具業界の鮎釣りトーナメントが年間8回もおこなわれている川もこの川だ
けの特徴となっているようです。いかにこの川の持つポテンシャルが高いかをこ
れは示していると思います。
山形随一といっていい、この川の魅力。これを本当に台無しにしてしまっていい
のでしょうか。
5年前の10月20日、私たち鶴岡市民は、月山ダムの事業によって、私たち
の誇りある水道水源を地下水100%の水道水からダムの水に切り替えられてし
まいました。
それと同様に私たち山形県民は、またも誇りある自然資源としての美しい川をダ
ムによって失おうとしているのです。
次の世代に何を手渡すべきか、コンクリートの山と借金の山か、それとも、美
しい山河か。いくら金をだしても買うことができない、貴重なバランスの上での
み成立する自然の美しさか。
今、私たちは問いかけられていると感じています。仕事になるといってもこう
したダム、ましてや穴開きダムの事業というのはできる建設会社は中央の大手の
ゼネコンだけです。もしかすると穴あきダム利権というのが芽生えているかもし
れません。地元業者は孫請け、ひ孫受けぐらいで、利益になる事業では決してな
いのではないでしょうか。先日ある方から、朝日村のあるホテルの話をうかがい
ました。そのホテルというのは、月山ダムの建設がおこなわれていた10年ほど
は一時的には潤っていたようですが、その間、一般の客の足が鈍り、ダム建設完
了後、ほぼ同時期に倒産してしまったということでした。
最上小国川の場合、赤倉温泉や瀬見温泉に宿泊する方の多くが鮎釣りに来る方
やこの清流の鮎を楽しみに来る方々だとうかがっています。これがダムによって
失われるとしたらどうでしょう。
また、歴史ある赤倉温泉、瀬見温泉の持続可能な振興策を考えれば、治水策を
めぐって、慎重にしっかりと議論し、考えなければならないと思っています。
10月28日のシンポジウムでは、徹底的にこの問題を検証し、真の治水につ
いて、全国的な見地で議論しあいます。ちらしなどは http: //www.ogunigawa.org
なお、本日の話ですが、はじめて参加される方もいらっしゃると思いましたの
で、今週月曜日に、県のほうから冒頭に説明してくれるように要請をしたのです
が、本日、「説明は尽くしている」などと断られました。全く不当な話です。
20日、八文字屋の前、以上の事などなど、1時間演説。終わる直前に大雨。ずぶ
ぬれになりましたが、新たな一歩に向けての禊ぎのよ うに感じられ、なんだかパ
ワーが増しています。
鶴岡の水道水については、この5年で市民の生活はいかに変わったのか。みなさ
んの声を伺って参ります。ぜひ、メールなどもお寄せいただければ幸いです。ま
た、28日のシンポもよろしくお願いします。
10月20日、月山ダム事業を教訓に公共事業を問う日。これからもまためいっぱい
動きだします。
薩摩琵琶とフルートのコンサート
お知らせが遅くなって失礼しました。
来る10月24日(火)
オランダ生まれ、スペイングラナダ在住のウイルオッフェルマンズ(フルート)と上田純子(薩摩琵琶)のデュオのコンサートが鶴岡であります。
場所は、鶴岡市大正庵。会費2000円
ウイルオッフェルマンズは、フルートの名手
http://www.wiloffermans.com/
上田純子氏は、薩摩琵琶で チェロのヨーヨーマとの共演などでも知られる、これもまた実力派。http://www.junkoueda.com/
今回、長崎と埼玉、鶴岡を結ぶツアーのために来日し、演奏します。
ぜひ、皆様お誘いあわせの上、おいでください。
プログラムは。
1.鶴の巣籠り
フルート・ソロ。
鶴の巣籠りは尺八ソロの伝統曲目である本曲の中でも特に有名な曲です。禅寺の様々な伝統の違いにより、現在10以上もの異なる解釈があります。タイトル「鶴の巣籠り」は、長寿と幸福のシンボルである鶴の一生を描写しています。番いの鶴が巣を作り、卵を温め、雛をかえし育て、子鶴が独り立ちするのを見送り、そして最後に番いはこの世を去ります。この曲は、鶴の鳴き声や羽音を尺八で模倣したりする自然表現の他に、番いの鶴が子を慎重に育てることによって表現される、仏教の哀れみの愛の観念の音楽的な明示であると解釈することもできます。今日お聴きいただきます鶴の巣籠りは、尺八の大家、横山勝也氏の演奏を、ウィル・オッフェルマンズが西洋のフルートのために写譜し、フルートの新しい可能性を発見しました。正に温故知新というべきでしょう。楽譜がドイツのツィマーマンより出版。
2.義経
琵琶古典語り。
平家物語の中では、義経は平家との戦いで源氏に勝利をもたらしたヒーローとして描写されています。平家の滅亡をもたらした壇ノ浦の合戦の後、源氏は鎌倉に幕府を置き、1192年より1333年までの鎌倉時代を開きました。そして、義経の兄にあたる頼朝が政権を握りました。義経は頼朝への忠実を誓うのですが、頼朝は義経がひそかに政権を奪おうとしているという疑いをかけます。そして、頼朝は義経を暗殺せよとの命令を出し、そのため義経は陸奥への逃亡の旅に出ることを余儀なくされます。この作品「義経」では、逃亡中の3つのエピソードが語られます。
- 舟弁慶
義経は彼の忠実な家来弁慶とともに、船にて大物の浦(瀬戸内海)を渡っています。途中嵐に巻き込まれ、そこに平家一族の幽霊があらわれます。壇ノ浦にて義経に殺された平家の大将平知盛の怨霊があらわれ、義経らが乗る船を転覆させようとします。弁慶が数珠を揉んで必死に祈り続け、ようやく嵐が静まります。
- 吉野静
義経一行が奈良の吉野に到着すると、そこで義経の恋人静が一行を待ち受けています。義経は静に難しい状況に直面していることを語り、彼の帰りを待つようにと告げます。そして別れの杯を交わします。
- 安宅
義経、弁慶と荷負人の一行は身を隠すため僧の姿に変装し、安宅の関に到着します。関首の富樫は、僧の姿の義経を疑わしく思い引き止めます。弁慶は義経を助けるため、師である義経を罵倒し、ムチで打ち付けます。状況を理解した富樫は、義経と師を思う弁慶の気持ちをあわれに思い、見ない振りをして義経一行を見逃します。九死に一生を得た義経は、弁慶を手を取り感謝の念を告げ、弁慶は泣きむせびます。そして再び、夜明け前の雨の中を陸奥に向けて逃亡の旅を続けます。
3.心の声 – Inner Voices
デュオ、親指笛サムピー&声
4.奥の細道
デュオ、琵琶/声&フルート
時は17世紀。松尾芭蕉と曾良の陸奥の旅の中で出会う様々な感動を、文と俳句で綴った旅行記。城跡に昔を思いひととき涙したり、絶景宇宙にしばしば浸ったり、道に迷って途方に暮れたり、貧しい宿に眠れぬ夜を過ごしたり、俳壇の友人の寛大なるもてなしに心を安めたり、自然の息吹きに耳を傾けたり、などの旅道中。芭蕉と曾良は夏の盛りに出羽三山を通過します。その時の三句を題材に演奏します。
涼しさやほの三日月の羽黒山
雲の峰いくつ崩れて月の山
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
5.ノベンバー・ステップス・カデンツァ/November Steps Cadenza
武満徹作曲(1967)/編曲:上田/オッフェルマンズ(1995)
デュオ/上田&オッフェルマンズ:薩摩琵琶&フルートこの曲は日本の20世紀を代表する作曲家、武満徹の作品「ノベンバー・ステップス」のカデンツァを編曲したものです。この曲はオーケストラと尺八、琵琶のために書かれました。そして鶴田錦史(琵琶)、横山勝也(尺八)により世界各国で演奏された現代音楽の古典ともいえる曲でしょう。この作品の中で武満は、西洋と東洋の音楽的な統合のプロセスに歴史的に多いに貢献しました。オリジナルのソリスト達の励ましも受け、ここでは武満の思考にフルートと琵琶への編曲を通してさらに形を与えていく試みをしています。
6.メイド・イン・ジャパン
フルート&シンセサイザーによる日本の歌
ー赤とんぼ
ー荒城の月
その他











