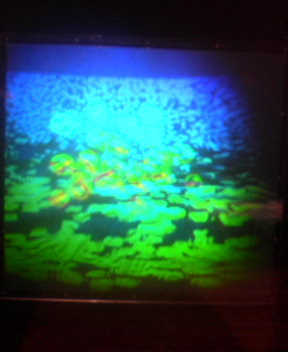共謀罪の審議 「まばたき」も成立!?
今日の法務委員会で、共謀罪が強行採決されるかもという事態が危惧されていました。
与党(自民党・公明党)は強行採決もほのめかしていたが、審議で同法案が持つ曖昧さがますます浮き彫りとなり、結局、採決まで至らなかったとのことでほっとしている。
動画による現状がわかる
http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/
をぜひチェック!
保坂議員の質問に、「共謀の合意は、めくばせでも、まばたきでもありえなくはない」と答える大林刑事局長。はあ?
今週金曜日にも強行可決される可能性もあり、さらに監視が必要だ。
小国川の事。
小国川漁協、神室の自然を守る会、出羽三山の自然を守る会のメンバーの皆さんと懇談。
穴あきダムの問題。以前、新聞クリッピングしたように、全国でブームのようである。
水を貯留するダムよりも流水型ダム(穴あきダム)の方が生態系に影響がない。
と推進派は言う。
しかし、水温が1度でも違っても、鮎には影響がある。水量が変化して石が泥で覆われる月山ダム建設後の赤川のようになれば、鮎は成長が遅れ、そして良質の苔を食べている鮎とは全く違った味になる。
それに穴あきダムだったら、全く土砂やヘドロが堆積しないのだろうか。小国川ダムの場合、現在示されている値では2.5m×2.5mの穴があいているだけなのだという。
ダムと堆砂、ヘドロの件については、富山の出平ダムや宇奈月ダムで訴訟問題がおきている。
以下、最新の取り組みがちょうどメールにて流れて来たので転載します。
——————————————————————–
黒部川の排砂問題に関心を持つ皆さんへ
「黒部川排砂ダム被害支援ネットワーク」よりお願い(転送歓迎します)
□5月29日〜31日 公害等調整委員会の証人・本人訊問に傍聴をお願いします。
弁護団報告にあるように今月29〜31日の3日間連続して証人・本人尋問が行われま
す。これは今回の公害等調整委員会そして、第一審の最大の山場になると思われま
す。6人の弁護士が弁護団を組み排砂と漁業被害との因果関係について最大限の立証
を進めてきましたが、本件の審理を担当する委員長は、「よみがえれ有明海訴訟」の
原因裁定で因果関係を否定した委員会の委員長と同じ方でであり予断は許されませ
ん。多くの傍聴者に集まっていただき、今回の裁判や公害等調整委員会に世論の関心
が高く厳正な判断を求めている事を示していかなければなりません。委員会の場に足
を運んでいただき、原告や証人の方を励ましていただきたいと思います。みなさん、
ぜひお越しください。
●場所…東京都千代田区霞が関3−1−1
中央合同庁舎第4号館10階1045室
公害等調整委員会審問廷
●スケジュール
5月29日 13時15分〜
・青海忠久福井県立大学教授
黒部川と河口沿岸の海底調査結果、ヘドロの与える悪影響について
5月30日 10時30分〜
・田崎和江金沢大学理学部教授
黒部川と河口沿岸の海底調査結果、ヘドロの与える悪影響について
13時〜
松本英二名古屋大学教授
被告側の主張全般
5月31日午前10時30分〜
・証人審問 藤田大介氏
04年、05年の入善沖海底調査の結果。それまで見られなかったヘドロが多く見
られたこと等。
□なお、この間の裁判の経過と今回の証人・本人訊問の位置づけについて弁護団報告
を転載する。
黒部川排砂ダム被害事件の経過
出し平排砂ダム被害弁護団報告
1 公害等調整委員会での原因裁定手続きの経過
2004年8月3日に富山地裁から国の公害等調整委員会(千代田区霞が関3
−1−1中央合同庁舎第4号館10階。以下「公調委」)に対して、因果関係につい
ての原因裁定(公調委で因果関係の有無を判断する手続)を行うことが嘱託され、原
因裁定手続きが始められため、裁判の方は、3〜4月に一度その進行状況を確認する
ための期日がもたれるだけで、専ら公調委で次の事件の手続きが進められている。
平成16年(ゲ)第3号 原因裁定嘱託事件関係
原告 井田隆三外13名,被告 関西電力株式会社
裁定委員委員長加藤和夫,委員平石次郎,同田辺淳也
2 原告らの主張・立証活動のポイント
1991年以後の出し平ダムによる排砂と漁業被害の間の因果関係について原因裁
定を求める、この公調委における審問での主張・立証活動が最近の弁護団の中心的活
動であった。
この間金沢大学田崎和枝教授及び福井県立大学青海忠久教授らによる調査・研究活
動の成果を受け、被害発生のメカニズムを主張・立証することに力を注いできた。地
質学及び海洋資源学の専門家による論文等各種専門論文を証拠として提出して裁判官
や行政官出身である委員長らに説得的に主張・立証することは思いの外困難な作業で
あった。また、事件の直接の被害者は「いなくなった」「魚」であり,なおさら困難
が伴う。しかし、研究者、被害者、そして弁護団、支援者による検討の結果、被害発
生のメカニズムが、相当わかってきたと思われる。それは (1)ダムによってでき
た人工的涸沼内にダム周辺から枯死木,落 葉,表土などが流入,沈降し,ダム底に
堆積した。ダム底質は貧酸素状態であり、堆積物中の嫌気性微生物の働きにより還元
的状態となり有機物は半分解状態になっていく。また、ダム湖底では有機物などを抱
え込む性質を持つ粘土鉱物のスメクタイトが大量に存在しており、半分解状態の有機
物と混ざって大量に堆積している。
(2)通常ならこれら有機物や粘土はダム湖底にとどまるが、出し平ダムでは排砂
ゲートから排出されることにより,これら大量の有機物及び粘土を含む土砂が一挙に
黒部川を伝って富山湾に流れ込んだ。本来ダムがない状態であれば相当の期間にわ
たって、少しづつ海に流れ込む有機物が、ダムのために湖底に堆積されて半分解状態
になり、これが排砂によって一挙に大量に粘土類とともに海に放出されることにな
る。1回の排砂で出される有機懸濁物質の量は大阪湾全体に1年間で堆積する量の5
分の1ないし4分の1にまでのぼる。
(3)当該有機物を含んだ大量の土砂は,富山湾の西から東に向かう潮流,季節に
よって異なる海水の混合特性や水温、海底の地形などの要因のもとで、主として黒部
川河口北西部の海底のくぼみや谷すじに堆積する。堅く堆積した大量の有機物は貧酸
素状態のもとで微生物の働きで、半分解状態のために急速に魚に有害な硫化水素やア
ミン類、アルデヒド類などを発生させるとともに、海底直上水を貧酸素状態にする。
これにより,魚や底棲生物が斃死したり、忌避行動を起こすなどの悪影響を及ぼし
た。これら堆積物は,その起源分析によりダム由来物であることが判明している。
また、排砂時の浮泥や、一旦海底に堆積した粘土類、有機物が波浪などによって再
浮遊したものなどが、海藻や海藻が付着する岩石の表面を覆 い、その生育に悪影響を
及ぼし、養殖ワカメの漁獲を激減させ、海藻の減少のために小魚や魚の餌となる生物
がいなくなり、魚の生育環境を奪った。
というものである。
3 公調委での審問の状況
昨年は合計5回の審問が開かれたが、ほぼ裁判と同様の形の主張及び立証が求め
られた。その中では、海底がヘドロ化したというが、過去の海底の状況はどうだった
のか、どう変わったのか主張立証せよという困難な問いかけがあったり,もともと黒
部川以西は今回問題となっている黒部川以東に比べ泥質であるが,そこでは漁獲高が
減っていないのではないか,刺し網漁業者が主として取っていた「ひらめ」について
は漁獲量が激減したと言うが,全国的にも同様の漁獲減少傾向にあるのではないか
等,多種多様な反論もなされ,排砂と漁業被害との因果関係の存在をいかに認めさせ
るか弁護団会議で議論を闘わせてきた。
ただ、昨年秋以降県東部で例年にないヒラメの豊漁が報じられたが、豊漁だったの
は黒部川河口の西側だけで、以前ははるかにヒラメ漁獲が多かった東側では漁はな
かった。これも有力な根拠になると考えている。
4 損害立証の困難性
また,因果関係の解明が中心となる公調委の手続きではあるが、排砂とその結果と
して生じた被害、損害との間の因果関係が問題になる以上,魚が忌避ないし斃死した
という被害が生じていることを証明しなければならない。そのため漁業者の操業場所
における漁獲量が減少したことを主張・立証しなければならないが,これも容易な作
業ではない。そもそも刺し網漁業者には,従前は漁獲高・漁獲量を裏付ける資料を保
管するという必要性はなかったため、そのような習慣もなかったし,1991年に初
回の排砂が行われた時点や、その後数年間は,現在のような壊滅的な被害の発生を予
想しえなかったから、漁獲量の推移を記録したり、保存したりしていなかったためで
ある。また、漁業者の漁獲状況を把握しているはずの周辺の漁協も、排砂を認める県
漁連の影響のためか、協力的ではなく、原告らが尋ねても協力が得られる状況ではな
い。そのため弁護団として公調委に、周辺の漁協や魚市場に対して漁獲状況調査を実
施するよう働きかけるなど損害立証につき,さまざまな角度からの立証作業を試みて
いる。
5 被害者の誠実性と関電の不誠実性
当初から刺し網漁業者の方は,お金の問題ではなく、失われた漁場の回復を何とか
してほしいと一貫して訴え続けてきた。漁場さえ回復すればいくらでもやり直せる
し、富山県民の財産である「キトキト」の魚が戻るからである。そのため活動の中心
は,漁場回復を求める点にあり,それは現在も変わらない。
これに対して、被告関西電力は,「環境に配慮した排砂を目指したい」等と言いな
がら実際には、自らが組織している排砂評価委員会に被害者を参加させず、委員から
調査方法について疑問が出ても対応せず、極めて不十分な調査しか行わないで、調査
結果のデーターを盾に、排砂は影響を与えていない、との態度を崩さず現在に至って
も排砂方法の抜本的見直しや被害漁場回復のための方策をとっていない。
6 今後の手続きの見通し
公調委ではこれまでに9回の審問期日が開かれ、排砂と漁業被害との因果関係・科
学的メカニズムについて詳細な主張を求められてきた。こうして、因果関係に関する
主張が整理され、いよいよ5月29日から三日連続で田崎教授、青海教授、藤田教授
の研究者参考人と原告らの本人尋問が行われる。また、今後、専門委員による海底底
質調査が行われる見込みである。2003年以降の排砂量は9万、25万、51万
(各立方メートル)であったが、今年は3万立方メートルを予定しているとのことで
ある。排砂量が少ないことは富山湾の環境にとっては好ましいことではあるが、これ
は、公調委による底質調査を見越し、汚染データを出させないための関電側の策では
ないかと考えられないこともない。
最後に、初回排砂から約15年が経過し、漁の少ない中で大変な苦労をして漁業を
続けてこられた原告の方々も高齢になり,時間との勝負の面もある。最近の原油高は
漁業の継続にいっそうの困難をもたらしかねない。弁護団としても一丸となって早期
の解決に向け努力していく所存であり,引き続き支援をお願いする次第である。
以 上
発信先…排砂被害支援ネットワーク事務局長 金谷 敏行
水道ー酒田市松山町区が最高値
今朝の毎日新聞トップ記事は、水道料金7倍の差という記事だった。
以下、クリップします。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060514k0000m040104000c.html
水道料金:7倍以上の地域格差 8割以上の市が民間委託
全国779市と東京23区の水道料金に7倍以上もの地域格差があること
が、毎日新聞の調査で明らかになった。水道事業は原則として自治体が独立採
算制で運営しているが、規模や水源の得やすさに違いがある。過剰なダム開発や
節水技術の向上による水需要の減少で財政難に悩む自治体も多く、8割以上の
市は浄水場管理や料金徴収を民間委託し、経営効率の改善を図っていた。一方
で、「職員の技術力の低下」など、民間への依存を危惧(きぐ)する回答も目
立った。
調査は4月下旬から5月上旬にかけ、毎日新聞の支局などを通じて実施し
た。4月1日現在の水道料金や水道事業の民間委託状況を全市(複数の自治体
が作る水道企業団を含む)と東京都、千葉県、神奈川県に聞いた。
合併などの影響を考慮し、水道料金(簡易水道を除く)は1123地区
(東京23区は全体で1地区)に分けて分析した。一般家庭(水道口径13ミ
リ)が月に20トン使用した場合の料金(メーター代込み)は、最高が山形県酒田
市松山地区の6132円、最低が兵庫県赤穂市の829円、単純平均は2992円だった。
5000円以上は34地区で、27地区は北海道、東北、九州が占めた。
料金が安価な地区は富士山周辺など地下水が豊富な所が多かった。4000円
台は139地区、2000〜3000円台は825地区、2000円未満は125地区だった。
人口100万人以上の市は格差が小さく、最高が札幌市3486円、最低
は大阪市2016円。他に横浜市2578円、東京23区2309円だ。
一方、浄水場の管理や水質検査、水道メーターの検針、料金徴収など何ら
かの業務を一部でも民間に委託しているのは644市(企業団含む)と3都県
に上った。02年4月の改正水道法施行で、浄水場の運転や水質管理など技術
力を要する業務も民間企業に一括委託できるようになったことが委託を促進し
た。
委託業務がある市の9割以上は「経費節減」や「人員削減」につながった
と回答したが、一方で「専門技術が継承できない」「危機管理の対応が不十分
にな
る」など、自前の技術力の低下に懸念を示す市も48あった。
総務省によると、04年度は地方公営企業法が適用される1752水道事
業の20%は収支が赤字だった。日本水道協会によると、05年4月までの1
年間に93事業が料金を改定、平均値上げ率は5・9%だった。【まとめ・山本
建】
————————————————