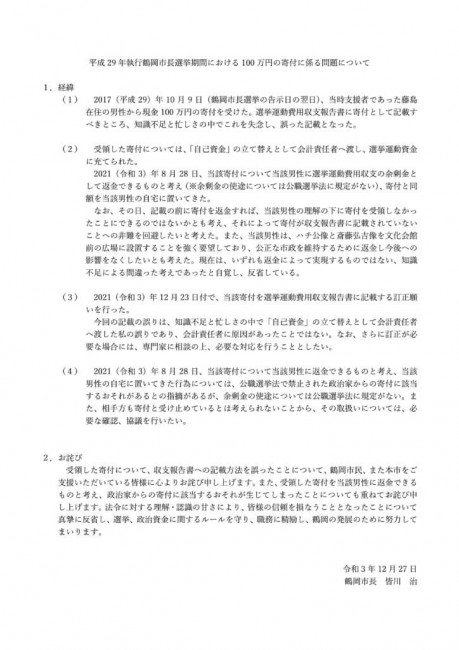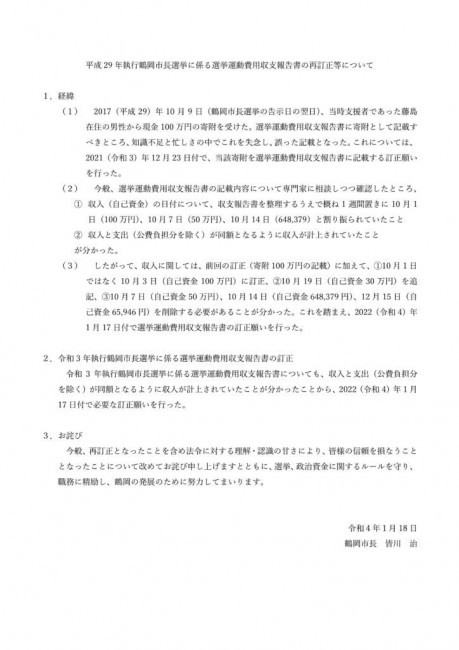1)災害時の水の確保 2)地下水活用について 3)脱炭素政策について 6月一般質問
1.災害時の水の確保について
災害時の水の確保についてお伺いします。
災害時において、ライフラインの断絶により一番困ったのは水の確保である。これはこれまで実際に震災を経験した方々の声であります。
厚生労働省による地震対策マニュアル策定指 針では、応急給水目標として、地震発生から3 日までは生命維持に必要な水量として、1人1 日3リットル、10日までは、最低限の生活を営 むために1人1日20リットル、21日までは、風 呂やシャワーを含めた水量として、1人1日 100リットルが想定されています。
今般はそうした災害時の水の確保をどのように想定しているのか確認したいと思います。
まず初めに、水道の耐震化についてお伺いします。
地震の際に耐え、水源から病院や二次避難所までをつなぐ耐震管路の目標として、どのような整備を考え、その進捗状況はいかがかお伺いします。また、配水池の耐震化はどのような段階かお伺いします。
次に、広域水道の断水時の想定です。
村山広域水道では、平成25年7月、豪雨によ る寒河江ダム湖周辺の土砂崩落などにより、ダ ム湖水の濁度が異常上昇しました。そのため、 下流から取水する村山広域水道の西川浄水場の 浄水能力を超える高濁度となり、天童市などで 最長で8日間にわたり断水する事態となりまし た。
あのときはこちら側の庄内南部広域水道でも月山ダム湖からの取水について、かなり濁度が上り、一時的に配水池への供給を中断したということも伺っておりました。こうした断水は十分に想定できることかと思います。
その後、村山広域水道では県による西川浄水場のハード整備、天童市では断水リスク軽減対策が策定されております。
そこでお伺いしますが、庄内南部広域水道が同様に濁度上昇などにより断水した際、当市ではどのように対処されるのかお伺いします。
次に、地震災害などによる水道管の切断時の際の飲料水の確保、また生活用水の確保についてはどのように想定されているか、上下水道部としての対応と、防災の面からどのような想定になっているのかお伺いします。
○上下水道部長 髙坂信司 災害時の水対策につ いてお答えします。
初めに、本市の耐震管路についてであります が、鶴岡市地域防災計画で庄内平野東縁断層帯 による地震のマグニチュードを7.5として、地震直後における上水道の被害を想定しており、 これを踏まえ、鶴岡市水道管路耐震化計画にお いて管路耐震化の目標を延長合計7万5,893メ ートルと定め、災害拠点病院及び市地域防災計 画の二次避難所のうち規模、立地条件等を考慮 して給水ラインの耐震整備を順次進めており、 令和3年度末現在の整備管路は9,517.1メート ル、全体の12.5%となっております。
配水池については、平成30年度から耐震整備 に着手し、全配水池の容量合計5万2,184立方 メートルに対して、令和3年度末現在、耐震整 備済みの配水池の容量合計は4万1,489立方メ ートルで耐震化率は79.5%となっております。
次に、庄内南部広域水道の濁度上昇などによる断水への対処方法についてお答えします。
広域水道の断水対策については、山形県が庄内広域水道受水地域における断水対策連携マニュアルを策定しており、これに基づいて段階的に対処してまいります。
第1段階では、濁度上昇前に広域水道の7つの受水地点の配水池において、高水位を確保し、並行して日本水道協会へ応援給水車の準備等を依頼します。
広域水道が給水制限となる段階では、必要水量の確保や必要に応じて応援給水車の派遣要請などを行います。
広域水道の断水時には、市民及び医療機関等への飲料水確保に努め、応援給水車等により確実かつ効果的に応急給水対策を実施します。
また、自己水源や予備水源の鶴岡浄水場を活用して、日頃より応急給水訓練を実施し、迅速に対処できるよう努めております。
次に、地震災害等による水道管切断時の対処方法についてでありますが、市地域防災計画に基づき、発災時は被害状況を迅速かつ的確に把握して、応急給水と応急復旧の計画を同時に立案し、応急対策を実行することとしております。
計画策定に当たり目標水準を定め、災害直後 72時間以内は市民の生命維持に必要な飲料水及 び医療機関等への給水を中心に行い、その後は 拠点給水、仮設給水栓等により飲料水等の供給 量を確保し、できるだけ早い段階での全戸給水 を目指してまいります。
応急給水に当たっては、広域水道の断水時と同様に、日本水道協会等の応援も得ながら給水対策を実施する一方、応急復旧については被害状況を踏まえて、水道管路網を解析し、断水範囲が最小限となるように水道管の制水弁を操作し、破損した水道施設を極力速やかに修復いたします。
また、各地域の拠点となる二次避難所11か所 にプールや雨水貯留槽の水を飲料できるように 浄化装置を配備しており、こうしたことも応急 給水計画の中で考慮して対処してまいります。
草島進一議員 耐震管についてはまだ12.5%ということで、 鋭意しっかりと今後進めていただきたいと思います。
生活用水については11か所でそういう浄水器 の対応ということですけれども、81か所、旧市内だけでもある二次避難所の対応、これがどうなのかなという感じもいたしました。
さらにこの水の確保についてお伺いしていき たいと思いますけれども、当市では平成25年に ミネラルウオーターを生産している企業などと 飲料水の災害協定を結んでおります。
先ほど御紹介した天童市の断水時では、市内の乳幼児がいらっしゃる御家庭にミルク用の水としてペットボトル水を配達したという事例がありました。
当市では災害時どのように活用する想定となっているのかお伺いしたいと思います。
また、災害時特に不自由したのが生活用水だったことは当時3か月断水した阪神・淡路大震災以来の災害からの教訓であります。
当時私も酒造会社の井戸に水をくみに行ったり、川で洗濯したりする光景をよく目にしておりました。
その後、災害時の応急給水用に防災用の井戸の活用が全国で進められております。
2007年7月の新潟県中越沖地震でも断水が3 週間続く中、消雪用井戸の多くが転用され、生 活用水で利用された。また、東日本大震災の際 にも、仙台市などで登録してあった災害応急用 井戸が貴重な水源になったと報告があります。
2021年、地下水学会誌の報告では地域防災計 画を公開している1,455自治体のうち75.6%の 1,316自治体の計画で井戸の利用について記載 があるということでした。
当市でも飲料水のほかにも工業用や消雪用などで数多く井戸の利用があります。こうした井戸を災害時協力井戸として登録を促し、協定を結び、防災マップ上に記載するなど活用を考えてはいかがでしょうか。見解をお伺いします。
○危機管理監 宮崎 哲 災害時の物資供給協定 企業から供給されるペットボトル水の活用想定 についてお答えをいたします。
現在、災害時にペットボトルの飲料水について供給協定を締結している企業は6企業あり、一部の協定企業とは供給物資の輸送方法についても協議しているところでございます。ペットボトル水については、運搬する車両も選ばず、水道施設復旧までの飲料水確保方法として有効な手段でありますので、避難所での活用を想定しており、避難所の状況について正確な情報収集に努め、飲料水が不足している避難所から優先的に配付し、有効に活用したいと考えております。なお、令和2年度の大雨被害の際、協定企業 から500ミリリットルのペットボトル水が384本 供給され、3か所の避難所に配付した実績がご ざいます。
被災の状況、規模により被災者の手元に飲料水が届くまで数日かかることも十分考えられますので、災害用の備蓄として飲料水については1人1日3リットルを3日分を自衛手段として各御家庭で御準備いただくよう、当市のホームページへの掲載のほか、講習会などで機会あるごとに周知のほうもしているところでございます。
災害時の民間所有井戸の活用についてお答えいたします。
災害時には大変有効な御提案だと伺いました。市では、現在鶴岡市内のどこにどのような規模の井戸がどのくらいあるかということを把握しておりませんので、また停電を伴った場合、井戸から水をくみ上げるポンプをどのように稼働させるか、水質の安全性など幾つか課題がございますので、今後情報収集をしながら、全国の先進事例などを参考にしながら研究をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○2番 草島進一議員 ありがとうございました。 今般いろいろ確認をすることができました。 災害に強いまちづくりとして水の確保は大変 重要でありまして、ぜひ生活用水の確保として、井戸の活用も計画に入れていただきながら、さらに充実を図っていただきたいと思います。ありがとうございました。
2)地下水の管理について
地下水の管理についてお伺いしたいと思います。
まず、地下水利用の現状についてお伺いをいたします。
まず、水道水源としては緊急用の1万トンの鶴岡水源、また旧櫛引地域約3,500トンの伏流水を活用した山添水源があると思います。現何本の井戸でくみ上げられ、ポンプのメンテナンスなど、どのような管理が行われているのかまずお伺いしたいと思います。
また、水源の地下水の管理としては涵養源と される河川や水田などの保全が大切と思います が、昭和55年の地下水調査の報告書の時点から 指摘されていたのが周辺地域の砂利採取による 地下水脈の破壊や水質低下でありました。
鶴岡水源周辺も水道水源として33本の井戸で 日量最大5万5,000トンほどくみ上げていた時 代は砂利採取がある程度規制されていたと思い ますが、水源切替え後、水源地周辺で相当数の 砂利採取工事が行われておりました。実際何件 程度行われたのかお伺いします。
また、影響が懸念されると指摘される砂利採取について、今後無制限に認めていいのかという課題は鶴岡、山添水源ともにあると思います。考え方をお伺いしたいと思います。
次に、全体の地下水管理についてお伺いします。
市内の地下水利用としては水道水源のほか、民間企業でミネラルウオーターの製造や酒造、工業用水、農業用水、消雪用水などとして利用しています。その揚水量の実態は把握されているのかお伺いします。
あとちょっと細かい質問になりますが、平成 31年の山形県の報告書にある鶴岡公園内で観測 している鶴岡第1号井戸の地下水位のグラフを 見ますと、水位データでは、平成19年以降、特 に冬場の水位の低下が見られ、累積地盤沈下量 の値では、平成20年から平成30年にかけ10年間 で20ミリ地盤が沈下していることが分かります。
この件について、市としてはどのように捉えているかお伺いします。
○上下水道部長 髙坂信司 鶴岡水源と山添水源 の取水井戸の本数と管理状況についてお答えし ます。
鶴岡水源は、非常用予備水源として6本の井戸から取水し、災害時に備えた週1回の浄水場のメンテナンス運転に併せてポンプの動作確認及び井戸水位等の巡視点検を実施しております。
また、山添水源は1本の井戸から取水し、常時遠方監視装置でポンプの運転状況及び井戸水位等を監視し、加えて週1回の巡視点検を実施しております。
○市民部長 伊藤慶也 続きまして、市民部より 砂利採取の状況等について、順次お答えさせて いただきます。
文書の保存期間もございまして、現在把握で きたものといたしましては、平成20年度から今 年4月までの件数となりますが、鶴岡水源周辺 における砂利採取は12か所でございます。
なお、山添水源周辺における砂利採取はございません。
次に、砂利採取の認可の制限についてお答えいたします。
砂利採取の認可につきましては、砂利採取業者が砂利採取法に基づき砂利採取計画について市町村からの意見を添えて県に申請し、県の認可を受ける必要がございます。砂利採取計画に対する本市の意見は、市関係課、土地改良区、農協及び生産者等で協議の上、県に申請しています。このことから、砂利採取については、市からの意見書を踏まえて県が審査を行い認可しているものと認識しております。
また、市では水源付近で砂利採取を行う業者、 事業者に対しましては、地表10メートル以内の 掘削にとどめていただくようお願いするなど、 水道水源付近の保全対策に努めております。
次に、地下水の揚水量についてお答えいたします。
現在、市において揚水量を把握しておりますのは、市が管理しております水道水源、それから鶴岡中央工業団地及び鶴岡西工業団地の揚水量となっております。
続きまして、県の観測データをどう捉えているかの御質問にお答えいたします。
県が設置している鶴岡1号井戸の観測データ の分析結果について、県より伺ったところ、地 盤の変動については平成17年あたりから僅かな がら沈下傾向にあったものの、環境省が沈下の 大きい地点の目安としている1年間の沈下量20 ミリに対して本市の場合は10年間で約20ミリと その数値を下回っており、また平成30年度は僅 かな地盤の上昇が見られること、加えて地下水 位については低下傾向が見られず、安定的に推 移していることから、県の見解といたしまして は、地盤沈下傾向は鎮静化していると判断し、 現時点においては地盤の調査は考えておらず、 監視を継続していくという方針であると伺って おります。
本市といたしましては、この分析結果を踏まえた県の見解と同様に認識しているところでございまして、引き続き鶴岡1号井戸の観測データによります地盤の変動と地下水位の動向を注視してまいりたいと存じます。以上でございます。
○2番 草島進一議員
ありがとうございます。 申請案件に応じた一定の条件や配慮事項を付し 鶴岡水源の6本の井戸、しっかりと今後も管 理していただきたいと思います。 また、櫛引、山添地域の市民の方々は、以前 と変わらず地下水由来の水道を利用しているわけでありまして、これは以前は多くの市民が享受していたおいしい水という貴重な地域特性として、この水源をしっかりと管理し、今後も維持して活用していただきたいと思います。
砂利採取については、平成20年から12件とい うことですが、今後についても注視していただきたいということです。
また、全体の地下水管理については、飲料水用と中央工業団地の水道しか管理していないということで、やはり井戸の多くが本数も箇所も揚水量も把握していないと。基本的に科学的管理されていないということが分かりました。
また、観測規制についてですけれども、平成 31年以降、ここ2年間は横ばい、あるいは上昇 ということで少し安堵をしましたけれども、た だ昭和50年代からずっと横ばいだったものがこ の10年で言わば2センチ地盤沈下が進行したこ とは事実であります。今後さらに沈下した場合、 現在井戸の本数も設置箇所も揚水量も実態が分 からない現状では科学的な対処ができないので はないかと考えます。
鶴岡の地下水については、以前、福島大学柴 崎研究室に依頼をし、2010年の卒論研究で現地 調査、水収支のシミュレーションをしていただ き、その成果について、2015年報告をいただい た経緯があります。
その報告では、持続的に地下水を利用していくためには、地下水盆の状態を把握することが重要であり、そのためには正確な地下水利用実態を把握することが必要であること、また当市には地下水利用に関する条例がなく、地下水揚水量が把握されていないままでは過剰揚水による地盤沈下、水質の悪化などの地下水障害を引き起こす可能性があること、また特に消雪用の井戸、工業用水などの揚水量の把握の必要性、 また砂利採取への懸念が指摘されておりました。 また、2014年に施行された水循環基本法では、
基本理念として、水が国民共有の貴重な財産で あり、公共性の高いものであるとして示され、 さらに昨年、2021年6月の改正では、地下水の 適正な保全及び利用の条文が追記され、さらに 地下水の公共性が強調されております。
以上、研究者の問題提起や改正水循環基本法を踏まえた上でお伺いしたいと思います。今般一部動きがあり指摘をしました地盤沈下などを未然に防止するためにも、利用者に届出を義務づけるなどして、井戸の本数や揚水量の実態を把握されてはいかがかと思います。
それを具現化するためにも、改めて本市の地下水を公の水、また公共水として定義づけ、次世代にわたって科学的な保全と適正な利用を目的とする地下水保全条例の設置を提案いたします。御見解をお伺いします。
○市民部長 伊藤慶也 それでは、ただいま御質 問いただきました地下水採取に関する届出、ま た地下水保全条例の設置についてお答えいたし ます。
議員御提案のとおり、課題等については本市としても認識しております。
先ほどの答弁させていただいたことの繰り返しと一部なりますが、本市における地盤と地下水位の状況につきましては県の見解がございまして、その見解を踏まえまして本市といたしましては地下水採取の届出や井戸の本数、揚水量調査などについて、現時点においては新たな制度の検討や調査については行う予定はございません。
しかしながら、議員の御指摘にもありますように、地下水障害を未然に防止することの重要性は認識しているところでございまして、今後の地盤の変動と地下水位の動向に注視しながら、地下水保全条例につきましては調査研究してまいりたいと存じます。以上でございます。
○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 豊富で良質な地下水資源を有し、それを享受してきた我が鶴岡市でありますが、伝統的にと言っていいのか分かりませんが、科学的に管理保全が行われていない課題をずっと抱えたままであります。懸念材料としてはほかにも水ビジネスなどの乱開発への対策の課題もありまして、それも含めて条例の検討をぜひ検討、研究を行っていただけたらと思います。
また、研究者の方々の声にもぜひしっかりと耳を傾けていただければと思います。それを要望してこの質問を終わりたいと思います。
●参考動画 「福島大学 柴崎研究室「鶴岡の地下水」
3)脱炭素化政策についてお伺いします。
まず第1点、ソーラーシェアリングについて お伺いします。
ソーラーシェアリングについては、平成30年 9月に一度質問しておりますが、あれから3年 半ほど経過しましたので、改めて質問をさせて いただきます。
先日、酒田市平田地区で1年半ほど前から取り組まれている水田での営農型太陽光発電の現場を視察しました。発電の規模49.5キロワッ ト、短冊形のパネル672枚を設置したものであ りまして、年間推定8万キロワットアワー、支 柱は結構頑丈で、コンバインなど農業機械が入 れる高さと幅があり、庄内の冬場の風、積雪に も十分耐える強度が実証されておりました。
事業者の方にお伺いすれば、設備投資は約 1,500万円、FIT17円で年間約150万円の売電 収入があり、20年で3,000万円ほどの売電収入 が見込まれ、総額約1,000万円の収益が見込ま れると。現在、はえぬきを生産し、昨年就業実 績が9%減とのことでありました。
前回提案した際、市としては実証が可能か検討を進めてまいりたいとのことでしたが、市内での取組の状況、市の検討状況をお伺いします。 2点目に、昨年6月に策定された国の脱炭素 化ロードマップに基づいて、今年1月から脱炭 素先行地域の募集が行われ、この4月26件の選定が行われたとのことであります。
市の脱炭素に向けた取組について、またこの先行地域への応募についての考え方をお伺いしたいと思います。
○農林水産部長 佐藤龍一 農林水産部から1点 目の営農型太陽光発電、いわゆるソーラーシェアリングについてお答えいたします。
ソーラーシェアリングは、農作物を作付している圃場の上に太陽光パネルを設置して農産物の生産と発電を同時に行う営農形態でありまして、本市においては令和2年に1件、畑地に導入している例がございます。
そこで作付している作物はユーカリでありま して、発電設備の面積は14アールとなっており ます。
ソーラーシェアリングを行う際の課題といたしましては、近隣の農地へ影響を及ぼさないことや、発電設備を設置した農地からの収穫量を地域平均の8割以上確保するという必要があることなど、農地法上の制限がございます。
また、発電設備の導入費用が高額になるため、採算性を十分に検討した上で導入を進めていく必要がございます。
なお、農地から雑種地などに転用して太陽光 発電施設を設置している件数は、再生可能エネ ルギー固定価格買取制度、いわゆるFIT制度、 これが開始された平成24年度から令和3年度ま での10年間で、本市では13件、合計面積は約 1.2ヘクタールとなっております。
議員から御案内ありました酒田市平田地区での取組につきましては、山形大学農学部地域産学官連携協議会のプロジェクト事業として行われておりまして、その事業の経営的評価に関する報告書の中では、売電収入は営農型太陽光発電の収入の大部分を占めるため、収益性に及ぼす買取り価格の影響は大きいというふうに報告されております。
買取り価格につきましては、制度が開始され た平成24年度は平田地区と同規模の場合、1キ ロワットアワー当たり40円、これは税抜きでご ざいます。40円でありましたが、年々減少して おりまして、令和4年度は11円、令和5年度は 10円になることが国から示されております。
本市では周辺地域も含め、先行する事例の情報収集を行ってまいりましたが、このように買取り価格が下がっていく中で、導入費用が高額なソーラーシェアリングに農業者が取り組むことには慎重な判断が必要というふうに考えてございます。
今後も農業者から導入等の相談があった場合には、農地法上の制限や発電設備の下で栽培する作物、栽培技術などの情報提供を行ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
○市民部長 伊藤慶也
次に、市民部より脱炭素 先行地域への取組についてお答えいたします。 議員御案内のとおり、国は昨年6月に公表し た地域脱炭素ロードマップに基づき、2030年度 までの脱炭素化に取り組む脱炭素先行地域を募 集し、今年4月に公表されました第1回の選考 結果では、19道府県、26自治体が選定されてお ります。
この先行地域に選定されますと、自家消費型の太陽光発電や住宅建築物の省エネなど、脱炭素の基盤となる重点対策について、国より財政支援を受けることができます。
本市の脱炭素化の取組といたしましては、昨年4月に稼働したごみ焼却施設において、ごみを燃やした熱を利用しての発電を行い、その余剰電力を売電し、市内の小・中学校や廃棄物処理施設に供給するといった電力の地産地消に取り組んでいるほか、災害時の避難所となる小・中学校等における太陽光発電設備や蓄電池など
の導入を推進しております。 また、民間においても櫛引地域での木質バイ オマス発電や昨年度には三瀬地区で風力発電が稼働を開始するなど、市内における脱炭素化に向けた取組が進められております。
本市の脱炭素化の施策につきましては、今後第2次総合計画の中間見直しと連動して、第3次鶴岡市地球温暖化対策実行計画の見直しを行います。その中で脱炭素先行地域の応募も含めまして、国の有利な支援制度の活用を十分検討しながら脱炭素化の実現に向けた施策や道筋を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
草島進一
ありがとうございました。 鶴岡の事業者にも確認しましたら、その方は FIT24円で年に約200万円ぐらいの売電収益があると伺っております。
酒田で水田、そして鶴岡で畑地の取組、ぜひ注視し、また可能性を探っていただきたいと思います。
FIT価格、今年11円でありますが、さらに 下がっていくと。このFIT価格低下の今後に ついては、ソーラーシェアリングも含めて全体 として新たな動きが始まっているようです。地 域マイクログリッドによる地産地消型、またP PAというモデル、フィードインプレミアム、 また大規模化など新たな方策の検討が始まって いるようです。
市内事業者からも御意見をお伺いしましたが、さらに大型化の普及なども検討しているようであります。これはより地域でいかに取り組むかということが問われている感じがしております。
この先行地域の事業立案についても共通して言えるんですけれども、このソーラーシェアリングを含め、ゼロカーボンに向けて地域主導でいかに再エネを増やしていくのか、市内企業、市民と共にこの最新のトレンドを踏まえながら、さらには開発による、今、風力発電とかでもいろいろ指摘されておりますけれども、開発による環境問題も踏まえながら、官民一体となって構想を練っていく新しい学習や協議の場が必要
ではないかと感じております。
ぜひそうした場をつくっていくことも要望し、質問を終わらせていただきます。ありがとうごさいました。
た。
議会議員自らが言論の機会を減らす暴挙 7/20 鶴岡市議会 議会運営委員会
【議会議員自らが言論の機会を減らす暴挙 7/20 鶴岡市議会議会運営委員会】
本日、議会運営委員会。総括質問の時間について、新政クラブの議員らが現在の時間配分では不平等だと主張し、これまで基本時間20分+議員一人あたり5分だった質問時間を、基本時間10分+議員一人あたり5分にすべしと提案をしていた事に対して議論した。
私は基本的に会派人数による「不平等」というよりも、主義主張を共にする会派としては、人数割りというよりも会派として平等に時間配分があってもいいという立場をとってきた。全国の議会を諸々調査してみると会派として人数に関係なく平等に時間配分している議会が結構あった。だから、これまで通り基本時間20分+一人5分のままでいいと主張してきた。
今般、新政クラブの提案について、改めて確認すると、質問時間が全体で1時間減ることが分かった。
新政クラブの団長に、「全体の議会の質問が減ることになるということは私は重大な事だと考えるが、それに対して どういう認識か?」と問うた。すると、「質問時間は重要なものだとは思ってはいる。全体の時間をどう保つかは議会運営委員会でおはかりいただいていいかと思う。我々は全体の格差というか比較の中で少ないという事で、その部分は今後議運や議会改革で議論すればいいのではないかと思う。」
と、なんら問題がないような答えが返ってきた。
私は、議会が自ら質問の時間を減らす。これは重大な問題だ。他の市議会では、例えば少数会派でも発言の機会を与えようと30分の時間を基本的に割り当てているところもある。
結局は、少数会派の言論封じなのではないか。と主張。石井議員は回答時間を含まない質問時間のみ時間制をとって言論の機会が減ることを防ぐことを主張。田中議員は更に検討が必要と主張した。
「会派の人数をもって平等性を主張されているけれども、私は調べる内に、少数会派の意見を尊重する等全国色々事例がありました。そうする内に一人あたりの平等性ということについても信憑性はどうなのか?とも考えました。全体の質問時間が減る。これはまさに言論封じとうことを自らが行うということにつながらないか。皆さんは平等性をうたって我々少数会派の時間を減らそうとしていますが、これは言論封じなんじゃないですか?
全体の議会制民主主義を担保する上で議会の質問というのは大変重要なんですよ。全国色々事例があるし議長会に調べてもらったら色々でてきますよ。うちの議会の常識だけで決めない方がいいと思います。」と主張した。
採決が行われ、石井、田中、草島が反対。新政クラブ尾形、渋谷、佐藤昌哉、佐藤博幸、五十嵐一彦、公明 黒井が賛成。(共産は菅井議員が委員長)
これによって、我々、市民の声・鶴岡の総括質問は30分から20分に減る。新政クラブは65分 共産党30分 公明党20分(副議長分が除かれる) 市民フォーラム、SDGs鶴ヶ丘 市民の声 各20分になる。
全体の質疑時間は今までよりも1時間減ってしまう。これは全国、議論を尽くそうと議会改革が進む中、当議会としては大いなる後退だ。
数の力をもって、自らの言論の機会を封じる議員達の暴挙に対して大いに抗議する。
1)酒井家入部400年記念事業の映像アーカイブ、配信について 2)米政策について 3)運輸業の支援について 6月議会総括質問
6月議会総括質問
草 島 進 一
初めに、酒井家庄内入部400年記念事業についてお伺いします。
昨年度約2,000万円、今年度約4,300万円の事 業が年度当初から本格化しております。
致道博物館での特別展、先週、大変興味深く 拝見をいたしました。5月7日には歴史シンポ ジウムが開催されましたし、また今週末には宝 生流の能楽公演などが行われます。大変楽しみ にもしておりますし、まずは御尽力いただいて いる関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思い ます。
この特設のホームページには、地域固有の歴 史や文化に対する理解を促進することで、郷土 への愛着と誇りを高めるとともに、その魅力を 広く国内外に発信することで、交流を拡大し、 次代を見据えた庄内及び鶴岡のさらなる発展を 図ることを目的としますとあります。今回は、 その趣旨を受け止めた上で、この一連の事業の 記録、情報発信、アーカイブについてどのよう にお考えなのか、改めて確認と提案を申し上げ たいと思います。
令和元年以降、ウイズコロナの時代となりま して、自治体主催の各種講演会のオンライン開 催、またハイブリッド開催、またアーカイブ配 信などが行われています。しかしながら、当市 の場合、昨年度プレイベントとして開催された 歴史講演会は現地開催のみであり、現在特設ペ ージにその模様が掲載されておりますが、講師 の方の顔写真は確認できますが、内容について は、その様子が一言のみ掲載されることになっております。
5月7日行われた歴史講演会は、タクト鶴岡での現地開催でありました。参加人数は約300 人と伺っております。単純に比較はできないと は思いますが、それと時を同じくして羽黒地区 のいでは文化記念館で行われた修験道と精神文 化をテーマとした講演会は一律有料のシンポジ ウムでしたが、現地50名、オンライン参加550 名という開催状況でありました。
また、7月11日には、東京開催のシンポジウ ムを予定しているわけですが、観光誘客や交流 拡大のための東京開催の意義は一定の理解をす るものの、現状のままですと、納税者である市 民が全く参加できないという課題を抱えている と考えますし、交流人口拡大を目的としながら、 その場限りのイベントで果たしていいのだろう かと感じました。
そこで、講演会の動画のアーカイブ配信につ いて、全国の事例を調べてみました。様々な自 治体で歴史講演会、防災講演会などの動画アー カイブの配信が行われているようですが、特に 岐阜市で行われている織田信長をテーマにした 信長学フォーラムの取組は参考になるのではな いかと思いました。
そのホームページには、市民の皆さんに御自 宅で楽しんでいただけるよう動画配信しますと あり、大河ドラマの時代考証を担当している著 名な大学名誉教授の基調講演や特別上演、また 新進気鋭の研究者によるパネルディスカッショ ンを見ることができます。基調講演は、約2万 件のアクセスがありました。
岐阜市の御担当にお伺いしてみたのですが、 フォーラムについては、基本的に映像を撮り公 開をしている。大学教授、時代小説作家などに 依頼しているが、これまで撮影、配信などで断 られたケースはないとのことでした。
お隣の酒田市でも、これはコロナ禍でのシン ポジウムですが、オンラインのみで行った酒田文化の融合観光フォーラム・日本遺産観光資源 活用研修会については、著名な元NHKアナウ ンサーによる歴史講演会や、酒田舞娘と東京芸 術大学のコラボ演奏の動画アーカイブが公開さ れ、今でも見ることができます。基調講演は、 約4,000弱ぐらいのアクセスがありました。
ほかに、例えば酒井忠次公を取り上げた歴史 講演会については、東京大学の准教授の講演を 愛知県安城市の歴史博物館配信のユーチューブ チャンネルで見ることができます。
要は、自治体の方針、裁量で講師の方々の了解を取れば、十分に可能だということだと思い ます。
そうした先例を踏まえて御提言申し上げたい のですが、今般実行委員会をはじめとして、 様々な主催団体が行う事業とは伺っております が、まずは基本方針として一連の事業、歴史講 演会、また能楽公演や催事など、しっかりと映 像に収めていただきたいということ。そして、 可能な限り動画コンテンツを市の公式ユーチュ ーブチャンネルなどで配信をして、市民をはじ め、より多くの全国の方々へ情報発信していた だくことを御提案申し上げたいと思います。
具体的に言えば、7月11日東京開催の講演会 は、できれば市民も見ることができるようにハ イブリット開催、あるいは後日編集からで結構 ですので、市民、全国の方々に向けて動画配信 するなどをしていただけないでしょうか。
また、例えば能楽公演についても、一般公開 されない奉納舞台などをはじめ、独自に映像取 材を入れて、きちんと記録を残していただけな いでしょうか。これは、例えば後日有料のDV D化などを含めて御検討されることを希望いた します。
要は、講師の方々への依頼の際に、一歩踏み 込んでお願いをし、了解を取れば可能なことで ありますし、開催趣旨やウイズコロナ、またデ ジタル化社会を踏まえて、より多くの方が参加できるように、新たな基本方針を持って取り組 んでいただけないかと思います。
また、映像撮影やユーチューブ放映に関して は、市の独自メディア機関として鶴岡ケーブル テレビに機材もプロのスタッフもいらっしゃる わけですので、ぜひこの機会にフルにコミットしていただき、櫛引、朝日地区へのケーブルテレビでも記念事業を放映するとともに、ネット 配信をしていただくなど行ってはどうかと考え ます。
以上、提案を申し上げますが、市長の見解を お伺いしたいと思います。
○市長 皆川 治
草島進一議員さんからの総括質問に対しまして、順次お答えをいたします。 酒井家庄内入部400年記念事業における講演 会などでの動画撮影、配信、アーカイブ化につ いてのお尋ねがございました。議員からは、こ のアーカイブ化については、これまでもお話が ありまして、またこのたびも大変重要な提言だというふうに受け止めております。 記念事業におきましては、酒井家400年の歩みと重なる歴史と文化の学びを深める講演会や シンポジウムなどを行っており、記録用として 動画を撮影し、保存しているところでございま す。記念事業における講演会などの内容の公開 に当たりましては、こうした動画記録のインタ ーネット配信を基本としながら、その都度講師 の皆様と御相談した上で、その方針を検討して いるところでございます。
昨年9月18日に開催いたしました松ヶ岡開墾 150年記念トークショーにおきましては、登壇 者のお二人から御承諾を得た上で、動画を撮影、 配信を行い、現在も市のホームページで公開し ております。
一方で、先月5月7日に開催しました歴史シ ンポジウムにつきましては、講師の先生から御承諾を得られず、動画記録の配信は見送りした ものでありますが、改めて市郷土資料館におい て、講演録を発行、販売する予定でございます。
来月11日に開催を予定しております東京での シンポジウムなどにおきましても、動画を記録、 保存しますが、公開手法につきましては、講師 の皆様と御相談することとしております。宝生 流能楽公演など、民間団体における取組へも動 画の記録保存や積極的な活用をお願いしてまい ります。
また、市のケーブルテレビジョンとも記念事 業の取組を共有し、地域での情報発信の強化を 図ることとしております。
今後も「400年から学ぶ庄内 みんなでつな ごう将来」をキャッチフレーズとして、講演会 などの学びの成果につきましては、動画記録を 活用しながら次代に継承してまいります。
草島
次に、農政についてお伺いします。
昨年、生え抜きで2,200円もの概算価格の下 落というのは、多くの農業者の皆さんにとって 大変深刻なものであったと思います。市・県の 一連の支援策は行われたわけですが、さらに動 向を注視していく必要があると思います。
そこでお伺いしますが、令和3年の米価下落 を受けてのならし対策の発動見込みはいかがで しょうか、お伺いします。
また、今年さらに米価の下落も懸念される中、 ウクライナ情勢などによる原油高騰、物価の上 昇など、所得確保に向けて厳しい環境の中、米 農家の所得確保について、どのように考えてお られるか、生産調整の令和4年の見込みはどう かお伺いします。
また、中長期的に米生産の構造を変えていく 中で、令和4年の生産調整はどのように進めて いこうとしているのかお伺いします。
市長 農業施策についての御質問にお答えを いたします。
最初に、ならし対策についてでございますが、 令和3年産米の価格が大幅に下落したことによ り、本県では当年産収入額が過去の平均収入額 を下回ったことを受け、収入減少影響緩和交付 金、いわゆるならし対策が発動されることとな りました。これによりまして、加入農家には6 月下旬に補填金、約1,000人に対しまして、約 7億円が交付される見込みとなっております。
こうした中、米価下落の懸念とともに、ロシ アのウクライナ侵略も長くなってきておりまし て、JAが所管する共同乾燥施設や生産者が所 有している乾燥調整施設などの電気代や燃料代、 さらには肥料や農業用資材などの高騰によって、 米農家へのさらなる影響が危惧されるところで あります。
今後、米農家の所得を確保するためには、影 響を一時的に緩和する対策とともに、これまで 以上に水田農業の収益性の向上を図っていくこ とが重要と考えております。そのため、国の水田活用の直接支払交付金や水田リノベーション 事業などを効果的に活用して、加工用米や輸出 用米などの非主食用米や大豆、高収益作物など への転換を強化していく必要があります。こう した取組を着実に進めてまいりたいと考えてお ります。
本市における令和4年産主食用米の生産の目 安につきましては、前年比で439ヘクタール減 少し、8,726ヘクタールとなりました。市とし ましては、JAなど関係機関と連携し、国や県 の支援制度を活用しながら、先ほど申し上げま した加工用米や輸出用米などの非主食用米、大 豆、園芸作物などへの転換により、生産の目安 は達成されるものと考えております。
次に、中長期的な生産調整の展望についてで ございますが、本市は水田農業に適した土地柄 であり、水稲を主とする営農形態が定着してお ります。このため、本市の水田収益力強化ビジ ョンにおいて、米に加え大豆やソバ、エダマメ 等の転作作物など、水田をフル活用した作物の 作付に取り組むこととしており、市内の約1万 5,000ヘクタールの水田のうちおよそ4分の3 に当たる約1万1,400ヘクタールにつきまして は、非主食用米を含めた水稲作付を維持してお ります。その中で、農家戸数の減少により、経 営体当たりの経営面積が増加していることから、 特に比較的作業時間が少なく、価格も安定して いる大豆の作付を積極的に進めていきたいと考 えております。
国では、麦、大豆の需要を捉えた生産を推進 するために、中長期的な事業として麦・大豆収 益性生産向上プロジェクトを実施しております。 本市におきましても、こうした事業を活用し、 JAと連携しながら大豆の生産拡大のための環 境整備を進め、水稲との団地輪作体系による転 作拡大を図ってまいります。
さらには、産地交付金や水田畑地化事業など を有効に活用しながら、収益性の高い園芸作物への転換も支援することによって、安定的な生 産調整を目指してまいります。
草島
次に、運送業者の原油価格高騰対策事業につ いてお伺いします。
原産国による原油供給の不足、またウクライ ナ情勢によりガソリン価格や原油価格の大幅な 高騰が続いており、この間、山形県トラック協 会からも要望が出されている中で、今般提案の 対策がなされることは大変評価をいたしますし、運送業の方々からは県の支援事業も含めて大変 ありがたいとの声をいただいております。
そこで質問いたします。
今般の市の対策では、大型車、普通車、1台 3万円、軽自動車5,000円の支援ということで すが、金額設定の根拠をまずお伺いします。
また、当市の支援では、県の支援策には含ま れていない軽自動車運送事業も含んでおります が、制度設計の意図をお伺いしたいと思います。
また、説明資料には、条件としてポストコロ ナ、ウイズコロナ対策として省エネ技術の導入 の取組が掲げられておりますが、その意図をお 伺いしたいと思います。以上、質問いたします。
市長
続きまして、運送事業者への支援についてで ありますが、トラックなど貨物輸送業者はイン ターネット販売や宅配が定着する中で、市民の 皆様にとっても必要不可欠な生活機能の一部と なっております。コロナ禍において企業活動が 一部停滞し、輸送量が減少したことに加え、石 油原産国による供給不足とウクライナ情勢もあ り、燃油価格が上昇したことから、経営環境は 悪化しております。国においても石油元に対す る補助金により、燃油価格の上昇を抑制してお りますが、いまだ高い水準にとどまっておりま す。
こうしたことから、市といたしましては、原 油価格の高騰の影響を受けた運送事業者の負担 軽減を図り、経営継続を支援することで、地域 の安定的な物流を確保するため、本議会に関連 予算を計上したところでございます。
具体的には、トラック1台当たり3か月分の 燃料費用の4分の1程度として、トラックは3 万円、軽貨物は5,000円の支援金を支給するも のであります。県でも同様に、トラックに対し ては3か月分の燃料費用の2分の1程度として、 6万円の助成が県議会6月補正に盛り込まれて いるところでございます。県では、軽貨物は対 象外とするようでありますけれども、他人の需 要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送 する事業者としては、トラックも軽貨物も地域 の物流を支える役割は同じでありますので、市ではいずれも対象としたところでございます。
また、省エネ技術等の導入など、ポストコロ ナ、ウイズコロナに向けた取組を支給の要件の 一つとしておりますが、今後も燃油価格が下が るかどうかは不透明であり、持続可能な経営の ためには、生産性を上げ、経営体質を強化して いただくことも重要でございます。このため、 作業能力の向上や生産設備の効率化に取り組むこと。一例としましては、デジタルタコメータ ーの導入や運行管理のデジタル化に取り組む。 あるいはエコドライブ運転研修会への参加など による省エネへの取組を要件とするよう検討し ているところでございます。
保護中: 鶴岡市議会 政務活動費不適切受給問題 タイムライン
2022参議院選挙、私の選択肢。
2022参議院選挙、私の選択肢。
皆様へ
いつもご支援、応援をいただき、ありがとうございます。
今年6月22日公示、7月10日投票の 参議院選挙の私の行動と選択肢について お伝えいたします。
皆様の投票の際に、参考にしていただければ幸いです。
1.消費税減税の為に自公以外を。
今般の参議院選挙は、先ずは第一点は、円安が進み、それに伴う物価の高騰が顕在化している事に対し、これまでと同様の経済政策のまま「岸田インフレ」を更に助長し、物価高騰、賃金そのままという状況のままでいいか。
それとも積極財政に転換し、消費税5%への減税などを実現し、負担を減らし、暮らしを守る社会に変えるか。
特に、自民党、公明党の他の野党が皆、消費税5%への減税を訴えています。
政府自民党が主張しているように社会保障のみに使われてきたかといえば、現実には、法人減税の穴埋めに7割以上も使われてきたという事が明らかになりました。特に日曜討論での自民党の高市早苗とれいわ新選組の大石あきこの対決としてネット上でも話題となりました。この映像では長年政府自民党が説明してきた「社会保障費のみに使われてきた」ということのウソが暴かれています。
参考動画
要するに、自民党が主張してきた消費税のウソが鮮明になったということです。
又、自公が勝てば、インボイス制度が実施され、免税事業者が実質廃止され、実質上の増税になります。
更に防衛費などの為に増税がおこなわれる可能性が高くなります。
物価対策として効果的で諸外国で当然のようにおこなわれている 消費税減を実現するには自公の他の野党に投票していただく事だと思います。
2.憲法改悪(9条改憲)阻止のために、自公維新以外を。
又、もうひとつ。憲法改正が重要な争点であると考えています。今回の選挙を過ぎると3年間国会議員の選挙がありません。その為、改憲勢力にとっては格好の契機であるとされています。
政府、自民党は、ロシアのウクライナ侵略とコロナウイルスの蔓延をきっかけに改憲や敵基地攻撃能力、核共有論などを主張しています。
また、現在、国会では、毎週憲法審査会がおこなわれるようになり注視しているところですが、最近の自民党は真っ正面から憲法に自衛隊を明記をし、国防を規定する事や緊急事態条項をいれることを訴えています。
自衛隊明記について、彼らは「9条そのものは変えず、ただ、自衛隊を明記するだけで憲法の基本の理念は変わらない」等と主張しています。
自民党作成の漫画「自衛隊明記ってなあに」 https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/constitution/kenpou_force.pdf
しかし、それはハッキリ言って嘘です。
自衛隊を明記すると
1)現憲法に規定されていない「国防」が正当化され、防衛費に際限の無い予算付けが認められ、結果として福祉、教育など国民の自由が制限されることになる。
2)2015年強行採決された平和安全法制整備法=「戦争法」の成立により集団的自衛権を限定的に認めており、明記により限定が外れ事実上通常の「軍隊」同様の扱いになり、他国から攻められる要因となる懸念がある。
など、前文や憲法9条で規定されている平和主義が根本から覆される重大な問題があります
更に自民党の公約には NATO 並みのGDP2%を念頭に防衛費の大幅増額が明記されています。
2%は11兆円。この額は世界第三位の軍事大国となる計算となります。この防衛費倍増については鶴岡市議会6月議会の討論でも述べましたが、現憲法に反するといわざるをえません。
現憲法下でもそのような主張をする自民党ですから、憲法に「自衛隊を明記」すれば国防の正統性を獲得し、憲法でも認める予算増となり、結果として国防により私たちの自由を縛ってしまうものになりかねません。平和国家から、戦前戦時の国防国家に戻ってしまうことになります。
法制定から75年たちますが、この間、私達の国は1度も戦争に巻き込まれることなく犠牲者を一人も出さずに平和を保ち続けてきました。「自衛隊の明記」は大戦を教訓に「国防」で国民の自由を制限する事を排し、個人の自由や平和を求め続けてきた現憲法の主旨を根本から完全に変える事になります。自衛隊は、明記しない事で「常に自衛のためか、必要最小限度かと問われ続けるとことに意味がある」のです。
(憲法学者 伊藤 真先生、小林 節先生の論文等より)
参考VTR
憲法は、国民が国家を縛るための法であり、国が国民を縛る法律とは違います。今の自民党他の改憲論者の主張は、国家権力をゆるめ、逆に国民の自由を縛ろうとしているとも感じられ、この立憲主義の憲法の大原則を歪めているとも感じています。
ウクライナ戦争での教訓は、改めて、専守防衛に徹し、平和憲法を活かした平和外交が必要な事。また今般真っ先に原発が攻撃、制圧された事を踏まえての脱原発であると考えます。
以上を踏まえ、私は今般の選挙では、投票用紙 2枚目の比例では、憲法9条を守り、脱原発を掲げる社民党 岡崎彩子さん、福島みずほさん、以前から環境政策の勉強仲間でもあった、れいわ新選組の長谷川ういこさんを応援しています。東京選挙区はれいわの山本太郎さん。立憲民主では、京都選挙区 福山哲朗さん、千葉選挙区 小西ひろゆきさんに更に活躍していただきたい(直接応援できませんが)。又、比例では辻元清美さんを応援しています。(今後比例の一票を決めますが)
又、1枚目の山形選挙区では、舟山やすえさんを応援しています。
正直、私は、国民民主党の特に国防論や憲法論、原発容認、予算賛成の姿勢には賛同できません。
しかしながら、某党の皆さんには申し訳ないのですが、実質的には、自民公明の巨大権力組織 対 舟山やすえと草の根市民の戦いであり、その選択肢として、舟山やすえさんを応援しています。
舟山やすえさんの選挙には18年前の初めての挑戦から応援し続けています。
北大農学部、農水官僚、又、ご家族で45haもの米と5haの大豆生産をされているということもあり、農政について、一貫して県内の農業生産者の現場の声に耳を傾け、個別所得補償制度、飼料米への転作、TPP反対、食料安全保障などの政策を進めてきました。ずっとその基本的な姿勢は変わっていません。鶴岡市、山形県の基幹産業である農業政策の現場の問題を解決し、さらに充実、発展させる為には舟山やすえさんの更なる活躍が必要と考えています。
国民民主党の玉木代表が主張する「反撃力」「原潜」まで展開する国防論、又、現憲法は規範力を失っている」と憲法審査会で表明し、緊急事態条項を主張し憲法改正を議論しようとする姿勢は、私には大変危険に映り、全く賛同できません。
ただし、国民民主の中でも差があり、玉木代表と舟山やすえさんの憲法に向かう姿勢は異なると感じています。
又、国民民主党の憲法論は、元衆議院議員の山尾しおりさんらが作成した、条文明記をして縛りをかける立憲的改憲論に基づいており、自民党の改憲案とは逆の方向だということを理解しています。しかしながら、その本質はメディアもほとんど扱わず、国民に理解が深まっているとは思えないし、実現性に乏しいと言わざるを得ません。圧倒的に自民党が強い国会の現状では、改正案として提案されるのは自民党案しか考えられないと思うのです。舟山さんには、そのこともお伝えしています。今後、憲法論について、県民とじっくり議論する場を設けてもらいたいと考えています。自民党よりは、大いに議論の余地があるということで支持をしています。
いずれにしても今回の選挙、自民党、公明党、維新に勝たせてしまうと、9条改憲の発議が起きかねません。平和国家から戦前の国防国家へ。平和主義、基本的人権の尊重、国民主権 というこの国の根幹が崩されかねないということです。
皆さん、ぜひそのことを、じっくり考えて投票していただきたいと思います。
くれぐれも棄権することのないように。棄権したら組織が強い自民党の勝利になります。
先ずは投票に行きましょう!
鶴岡市議会議員 草島進一 2022.6.30 7.9 改訂
ご覧いただきたい動画を紹介します。
1.9条改悪を絶対許すな!緊急集会
2.憲法を考える。
3.大変わかりやすい、伊藤真先生の憲法論。53分ぐらいから、自衛隊明記の問題を指摘しています。
4.憲法 守るべきものは何か 憲法学者 長谷部恭男先生と石川健治先生と、ウクライナ戦争後の憲法改正等の問題を考える。
○自衛隊を書き込めば、平和国家から国防国家へ逆戻り。その結果自由を奪いかねない
○緊急事態条項は危険。何のためにつくるのかがそもそもわからない
○異質な他者との共存できる場が破壊されかねない。
○条文が少なく、字数が少ないということで規律密度が低いということにはならない。
○憲法改正論者の多くは、憲法を国民の道徳だと思っている集団の中にあるように思える。
○小林節先生 冒頭に、自民党案のインチキを指摘しています。
加茂風力発電所計画とラムサール条約湿地 9月一般質問
原稿と書き起こした答弁です。(9/15 1;30更新)
草島 市民の声・鶴岡 草島進一です。
質問いたします。
先ず、加茂地区風力発電所計画について
今回は、野鳥の問題に絞って質問します。この間、ラムサール条約湿地であり、水鳥の集団渡来地としては県内唯一の国指定鳥獣保護区 特別保護地区 の大山上池・下池の野鳥の現況について、環境省の調査員の方にうかがいました。
コハクチョウ3千羽、マガモ 2万から3万羽の他、
国の天然記念物に指定されている 準絶滅危惧種 オオヒシクイ 1000羽、
絶滅危惧Ⅱ類のヒシクイ200羽 準絶滅危惧種 マガン200羽
珍しいものとしては、
絶滅危惧ⅠA類ハクガン30羽 まれにIA類 シジュウカラガンが観測されているとのこと。
又、高舘山と荒倉山の中間の建設予定地には絶滅危惧ⅠB類であるクマタカの営巣地があること。又、秋ごろからいずれも国の天然記念物の絶滅危惧ⅠB類 イヌワシ、絶滅危惧Ⅱ類のオオワシ、オジロワシが周辺で頻繁に見られるという事を確認しました。
現在 計189種の野鳥の生息が確認される国際的な特別保護地区であります。
風 力 発 電 が 鳥 類 に 与 え る 影 響 は 、2020年3月末時点で国内で580件発生しているバードストライクの問題。 生息地などの放棄。 渡りルートの変更など移動の障壁(しょうへき) と国内でも実例がある、3つの問題が指摘されています。
日本野鳥の会 山形支部からは、
●ハクチョウ類、ガン・カモ類の渡りルートとなっているため、飛行の際のバードストライクが発生する可能性がある。
●風車が飛行の障壁となり、渡りルートが変更になったり、越冬地が放棄される可能性がある。
●ミサゴやオオタカ、オジロワシ、オオワシといった 希少猛禽類が餌場として利用しており、特に猛禽類のバードストライクは、オジロワシで今年3月までで国内で70羽発生しており、クマタカでも国内事例がある。バードストライクや、餌場としての利用が減少してしまう可能性がある。
との見解をうかがっております。
日本野鳥の会からは、現在計画が進む 矢引風力発電事業に対して、「計画地は5k離れたラムサール条約湿地で越冬する野鳥たちが集結し、採餌する区域にあたり大きな影響を与える」との意見書が提出され、環境大臣 及び 経産大臣意見でも、想定区域の周辺には大山上池・ 下池が存在し、衝突事故など、影響が懸念される。鳥類に関する適切な 調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、鳥類への影響を回避 又は 極力低減すること。と要求されています。
今般の計画は条約湿地から2キロから3.5キロに8本、高さ最大で182m 出力6000kwと、三瀬の2倍の巨大な風車が立ち並ぶというものであります。
矢引の計画よりもさらに近く、更に大型の風車の建設は、バードストライクの発生する可能性が格段に高くなることが懸念され、「どれほど、野鳥に脅威となるか計り知れない」 との見解を野鳥の会の方から頂きました。
国内53箇所あるラムサール条約湿地に近接している風車について、環境省のご担当者に伺いましたが、「3例ほど、2012年に風力発電事業が環境アセス法の対象になる前にはあったものの、それ以降は、条約湿地から5k未満の建設はほとんどない」事を確認しております。
そこで質問します。
●先ず、今般の計画が、条約湿地に全国で最も近い場所での開発計画だという事への、市の認識をお尋ねします。
市民部長 事業の計画予定地につきましては、平成24年3月に公表された、山形県再生エネルギ-活用可能性報告書におきまして、大規模発電の候補地として抽出されているものの、ラムサール湿地が近傍であり、望ましくない。と注意書きを付して公表されております。
本市としても県の注意書きを踏まえ、しっかり鳥類等、自然環境や景観への影響を精査していく必要があると認識しております。
草島 現在、条約湿地から5kで計画が進む矢引の計画で、環境大臣 及び 経産大臣より意見された、条約湿地の鳥類への影響の回避には、どんな環境保全措置が示されたのか、伺います。
市民部長 次に三瀬矢引風力発電事業に関する質問にお答えします。
この計画については、すでに環境アセスメントの手続きが進められています。事業者より国、県、市に対して、環境配慮書が令和2年6月に、環境影響評価方法書が、同年11月に届け出されて、公告、縦覧がなされております。この方法書に対する県からの意見紹介に対して、市では環境審議会や庁内関係者と意見を集約し、県に提出しております。これを踏まえ、県ではラムサール条約湿地の鳥類等への影響の回避について、専門家等の知見、及び最新の情報を参考に調査し、事業による影響を回避又は提言することと、国に意見しております。
国ではこの県の意見を含め、方法書の審査をおこない、事業者に対し、県の意見書を添付して勧告がなされております。この勧告を受け、事業者では更に調査、予測及び評価を実施し、環境影響評価準備書を作成する流れとなっています。鳥類への影響の回避などについての措置については、今後提出されるその準備書において回答されることから、公表された際には市のホームページ等でお知らせすることとしております。
草島 又、加茂の計画の、今般提示した野鳥や、ラムサール条約湿地への影響を市としてどのように捉えているのか、お伺いします。
市民部長 次に、絶滅危惧種を含む野鳥やラムサール条約湿地への影響についてでございますが 当該地の登録基準といたしまして、大山上池下池は、定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地に該当しております。このため、ご指摘のバードストライクの発生や、湿地への飛来ルートへの影響、水鳥などの減少、また、自然環境の影響などについて、国や県にも確認しながら検討していく必要があると考えております。
草島 市では2020年12月に、出羽三山と金峰山に関連する区域の風力発電所の設置を認めないとして、ガイドライン上で制限区域を定めました。私は、ラムサール条約湿地を中核として、自然保護行政を進めてきた市として、予防原則に立って、「ラムサール条約湿地については、野鳥へ重大な影響が及ぶと考え得る 5K半径のバッファゾーンを含めて、設置を認めない」と、ガイドラインに加えること。
そして、開発業者に対しては、計画中止を促すなど、早期に意志表明をおこなう事を求めます。 見解をうかがいます。
市民部長 最後に市ガイドラインに制限している対象地域に加えることと、計画の早期撤退を促す意志表明についてお答えいたします。
本市ガイドラインの制限対象区域として、具体的に例示している区域は、出羽三山および金峰山に関連する区域となっております。同じく、制限対象区域としては、本市の豊かな自然環境や、歴史文化的資源から構成される良好な景観を形成する地域としており、この度の計画区域につきましては、ラムサール条約登録湿地に近接していることなどから、その区域に該当する可能性がございます。したがって、住民の同意や鳥類などの生態系及び景観等への影響について、専門家等にも相談して慎重に判断ていく必要があると考えております。
本市の計画に対する意志表明といたしましては、先ずは、現在事業者が風況調査と環境アセスメントの実施にかかる住民同意を得るために、住民説明会を開催しておりますので、その動向を注視してまいります。
草島 この風車建設は、認めれば全国初の事例となり、もし影響が生じれば全国、又、国際的に、非難の対象となりかねません。条約委員会が発行する「生態学的特徴を損なうような変化が既に起こっている、または起こりつつある、起こるおそれがある条約湿地のリスト」である、「モントルーレコード」へ掲載される事例になるではないか、と危惧するものです。見解を求めます。
●市民部長 この度の計画区域につきましては、ラムサール条約湿地に近接していることなどから、その区域に該当する可能性がございます。従って、住民の同意や、鳥類などの生態系、及び景観等への影響について、専門家等へも相談して慎重に判断していく必要があると考えております
草島 先ほど調査が必要というお答えが部長からありました。この調査の考え方として一点、環境アセス上の調査を進める上での判断という見方もあろうかと思います。しかしながらですね。矢引の計画の時点で、環境大臣及び経産大臣の意見書で影響が懸念されるとあり、鳥類に関する適切な調査が求められております。既に業者には、このラムサール条約湿地周辺の生息状況、営巣地、飛行経路など、詳細の調査が既に課せられていると思います。市としては、この矢引の計画段階で、事業者にラムサール条約湿地周辺の調査を十分におこなわせ、その資料を公開することを、要求すべきと考えますが、見解をお伺いしたいと想います。
市民部長 先ほども、環境アセスメントの手続きに関してはお答えいたしましたけれども、評価書の段階、それから方法書、ともに公表をされております。縦覧期間も終えておりますので、そこで一定の説明がなされたものと認識しております。尚、国からの勧告をうけまして、また、更にそれに対する回答がこれからなされますので、その際には住民の皆さんにもその事をお知らせしながら、ぜひその縦覧に対してよくご覧頂けるようにご紹介してまいりたいと思います。
草島 加茂の計画に踏み込む前にですね。矢引の段階でしっかりと調査を求め、判断の基準にしていただきたいと思います。
私は、市全体として、ラムサール条約湿地の認識不足を感じています。
現在、住民に対して開発側の説明はおこなわれていますが、ラムサール条約委員会や野鳥保護の立場での説明はおこなわれておりません。今後、市民や市が検討・判断をおこなうにあたり、環境審議会に環境省のラムサール条約湿地のご担当と、野鳥と風力発電の問題に精通した有識者を招き、審議頂く事。またその方々から市民への説明会を行なって頂くことを求めます。見解を求めます。
●市民部長 ただいま、環境審議会に有識者を招く事、それから市民への説明会についてご質問がございました。繰りかえしとはなりますが、現在開催しております、住民説明会の動向を注視しているところでございますけれども、議員ご提案につきましては、専門家とも良く相談しながら必要な助言を受けて参りたいと存じます。以上です。
草島 この問題は地元住民だけの問題ではなく市全体の環境政策の問題です。
今、提案した説明会も、今後の業者の説明会も、審議会も、多くの市民が関われるよう、完全公開、録画や配信などが可能な形での開催を求めます。
環境アセス上で、開発業者が依頼する鳥類の調査は、長期にわたって野鳥を網羅的に調査するものではなく、決して十分なものではありません。アセスに踏み込むなら、市独自の調査も必要です。又、アセス上の意見に対する配慮には「建設中止」というゼロオプションは想定にありません。所詮、意見書への配慮として、当初からの想定の中で、風車の数を減らすとか位置を変える等というのが常套手段、ということを、長年アセスに関わってこられた有識者に伺っています。
●要するに、環境アセスの前段階で意思表示をおこなわず、アセスに踏み込めば、事業を概ね認めることになる。というのが通例 ということです。
矢引の計画で湿地周辺の調査報告を提出させ、それも判断材料にしつつ、国際的な保護区としてのラムサール条約の主旨を踏まえ、アセス前に「予防原則」にもとづいて、ガイドラインの制限区域を設定する、いわばゾーニングで判断するということを大原則にしていただきたい。と考えます。
●又、昨年10月に風力発電開発の環境アセス要件が1万から5万Kwに変わり、加茂の全体で4万KWの開発計画には法アセスが適用されません。矢引の計画までのような手順は義務ではなくなり、環境大臣や経産大臣の意見や勧告もなくなり、野鳥への影響調査は簡易になる可能性がある。このリスクも踏まえるべきと思います。
●風力発電施設の設置にあたっては、重要鳥類生息地や、鳥類が集まる場所、渡りの経路上、保全上重要な種が生息する場所などの、環境保全上重要な地域を、「事前に避けるべき」、と言う「予防原則」が、国際的な野鳥の保護機関である バードライフ・インターナショナルの勧告であります。
以上、しっかりと受け止めていただくことを強く要望します。
2)草島 次にラムサール条約湿地 自治体認証などの取り組みについて伺います。
今般の風車計画問題で再認識された感があるラムサール条約湿地ですが、今年は国内で2つニュースがありました。一つは今年5月スイスで開催された59回常設委員会で「ラムサール条約湿地 自治体認証制度」に新潟市及び 鹿児島県 出水(いずみ)市 の認証が決定した。という事であり、もう一つは、絶滅寸前だったシジュウカラガンを復活させた「日本がんを保護する会」会長の呉地正行 (くれちまさゆき)さんが、日本人で3人目のラムサール賞を受賞された事であります。
私は大山の上池・下池のラムサール条約湿地登録の提案を2001年3月議会でおこなっているのですが、その頃、足繁く現地にいらして情報提供いただいたのが呉地さんでありました。提案後、役所の同意、地元合意まで時間を要しましたが、
2008年に韓国での締結国会議で登録され、あれから12年。
拠点施設ほとりあ も、開設から10年を迎え、又、当市も未来都市であるSDGsの目標15で、湿地の生態系や保全が重要とあり、改めて再価値化する必要性を感じております。
湿地自治体認証制度は、湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体に対して認証されるものであり、「ほとりあ」でこの間実践してきた、湿地環境の保全活動、外来生物駆除による生物多様性の再生として、ザリガニやウシガエルを捕獲し食材として提供するなど、人と湿地の関係性の再構築に務めてきた活動を評価し発信することになると思います。
又、月山のちとうの、高原の湿地環境、西茨新田湿地、又、庄内平野に広がる水田の多面的機能にも新たな価値を与え、新たな国際的な自治体ネットワークの構築の取り組みとなると考えます。 ぜひ湿地自治体認証への登録を提案します。見解を求めます。
市民部長 ラムサール条約湿地自治体認証への登録についてお答えいたします。この自治体認証制度は、議員ご紹介のとおり、ラムサール条約常設委員会が湿地の保全再生、管理の地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する基準に基づき認証をおこなうものでございます。国内では2市が日本ではじめて承認され、国外をあわせると13カ国、25都市が認証されております。認証を受けた自治体では自治体のブランド化、地域における湿地の保全や懸命な利用の更なる推進が図られるものと認識しております。本市としては、認証を受けた自治体の取り組みや課題なども情報収集につとめ、地域関係者の意向も確認しながら、ほとりあ等の取り組みも含めまして、今後どのような活動ができるのか、先ずは調査、研究してまいりたいと考えております。
草島 ぜひよろしくお願いします。
●草島 次に西茨新田湿地の保全について伺います。この件は、2016年6月議会で
故 渡辺ひろい議員が質問されています。
西郷地域、平地でミズバショウが見られ、原生のハンノキ林があり、
貴重なチョウ ミドリシジミ がみられる 約4ヘクタールのエリアであり、
植物274種、オジロワシなどの猛禽類をはじめ121種の鳥類、昆虫は137種類、が観察される「庄内の原生風景」をとどめた湿地であります。
当市議会では平成9年3月にここの湿地林を天然記念物として保護する請願が提出され、全会一致で採択。その後、教育委員会が天然記念物指定に動いたものの
地元地権者の同意が得られず指定を断念、その後、調査報告書を作成するにとどめたとのことでありました。
長年にわたり西郷小学校の子ども達が「ミズバショウの里づくり」として、保全活動、環境教育の場として利用し、今も続いていると伺っています。
保全施策の必要性が、地元や研究者などから、ほぼ40年前から求められ続けているにもかかわらず、現在も開発危機に直面する民有地のまま、市としての保全施策がとられないままで経過してきました。
改めて市で所得するなどし「庄内の原生風景」を活かした自然公園として、保全、活用がはかれないか。例えば風力発電の開発業者に対し、ミチゲーション手法での代替自然(だいたいしぜん)の回復といった地域貢献、を促すなど、民間資金の活用も視野にいれ、ぜひ再度検討を求めたいと思います。見解を求めます
市民部長 それでは西茨新田湿地の保全、活用について、お答えいたします。
西茨新田湿地は現在、民間所有となっておりますが、議員ご紹介のとおり、西郷小学校の六年生が、自然環境学習の場として活用しているとうかがっております。本市といたしましては、当該湿地について、市が所有して自然公園として管理することは考えておりませんが、地域住民の意向を伺いながら、地域での保全や活用方法、また、議員ご紹介の地域貢献としての民間活力の活用などについて、現状の把握と課題整理を先ずはおこなって参りたいと考えております。以上でございます。
草島 生物多様性の全体量が減らないようにする、NO NET LOSS というのがあるんですけれども、どこかで開発をおこなわれたら、どこかで回復する。そういった発想の地域貢献を求めていく、新しい発想での取り組み、期待しております。
●草島 今年12月には国連生物多様性条約第15回締約国会議COP15がカナダで開かれます。2010年の愛知ターゲットの次の生物多様性の目標として、2030年までに損失をくい止め、陸と海の30%以上を保全、保護を目指す目標 30BY30(サーティバイサーティ)が決議される見通しであり、
国内でも、更に保護地域の拡充、生物多様性に貢献する場所の新たな認定、
が求められます。
高山帯から里山、湿地、海浜砂丘など、多様で豊かな生態系を有する当市として、こうした新たな目標も踏まえ、絶滅危惧の動植物の消滅を回避することは重要と考えますし、その為の基本的な計画である「生物多様性地域戦略」は必須だと考えます。
ぜひ自然度の高い各地域庁舎でも担当を決めるなどして調査をおこなうなど、策定に取り組んで頂きたいと考えます。見解を求めます。
市民部長 生物多様性地域戦略の策定、市民調査、情報収集などについてお答えいたします。 生物多様性の保全に取り組んでいくためには、市民の方に本市の多様な植生や課た、について知って頂き、身近な問題として理解を深めていただくことが、重要であると考えております。生物多様性地域戦略につきましては、現在策定中の第二次環境基本計画におきまして、一体的に策定することとしており、大きな柱の一つに位置づけることとしております。具体的なとりくみといたしましては、本市の生物多様性を身近に学ぶ事ができる、自然学習交流館 ほとりあ を最大限活用し、体験を通した自然学週を推進していくとともに、地域固有の希少種生物などの多様性の保全に取り組んで参ります。今後とも地域調査とも連携をはかり、地域の資源調査や、情報収集につとめるとともに、幅広い世代の皆様により本市の生物多様性について、触れて学ぶ機会を創設し、市民への意識啓発や醸成を図って参りたいと考えております。以上でございます。
草島 ぜひ、しっかりと取り組んで頂きたいと思います。1と2 ここまでの議論もふまえて、市長にお伺いしたいとます。
風力発電事業ですが、上池・下池から5Kmの矢引の計画の時点で、環境大臣も経産大臣も野鳥への影響を懸念し、調査を求めていますし、私も懸念しています。でも矢引までは、ぎりぎり認めたいと思います。再エネは進めたいですから。でもその先は絶対NGです。地域還元の薄い植民地型開発、という点でも、矢引までにしていただきたい。と思います。
国際的な保護地域であるラムサール条約湿地と半径5kmのバッファゾーンは、30 By 30を踏まえた新たな保全地域として認定登録するなどをおこない、善寶寺から高舘、荒倉、由良までを結ぶ ブナ林の自然豊かな14Kmを散策できる 通称 「庄内海岸アルプスロード」を、新しいハイキングトレイルとして認め、発信するなど、「ラムサール条約湿地がある鶴岡」だからこそできる生物多様性戦略を前に進めて頂きたいと思います。市長の見解をうかがいます。
市長 今、草島進一議員さんからご質問をいただいた点でございますけれども、今、議員が2001年3月議会でラムサール条約の指定について、提案をされていたということ、について、改めて敬意を表する次第でございます。国際的な動向、30by30のお話もございましたけれども、この生物多様性戦略、大変重要だと私も受け止めております。この度の計画はラムサール登録湿地の大山上池・下池自然休養林の高舘山に近接しておりまして、多様な動植物の生態系が活用されている大変重要な場所でございます。また、環境大臣、経産大臣についてのお話もありましたけれども、山形県におきましても、平成20年3月の報告書におきまして、ラムサール湿地が近傍であり、望ましくないというような注意書きを付して風力の候補地の抽出がおこなわれております。この現在ですね、地元の説明会、住民説明会がおこなわれているところでございますので、先ず住民の合意のゆくえも注意しつつ、そして、国や県、そして専門家にも十分ご意見を頂いて、この生物多様性ということに十分配慮した取り組みを推進していく必要があると認識をしております。
舟山やすえ は、何を訴えてきたか。映像で見る参議院選挙2022
舟山やすえ 当選!
当選御礼の弁です。
参議院選挙2022 投票日は、7月10日。
山形選挙区は 草の根市民、県民の代表、
舟山やすえ候補に一票を!
7.4三川橋×112号 午前7時45分。本人もつじ立ち
舟山PV
@鶴岡つじ立ちから8時を迎え、第一声
参議院議員として2期12年間、県内の農業の現場、災害被災地の現場、商店街、企業の現場に足を運び聞き取りつつ、農業関連では個別保障制度 飼料米への転作制度、反TPP等 、最近はガソリン高騰に対して値下げ等の政策提言をおこなってきた 舟山やすえ候補。
鶴岡市の農業、山形県の農業、日本の農業の発展には舟山やすえの活躍が欠かせません。
又、地域分権、地域主導の持続可能なまちづくりの為にも舟山やすえ の力が必要です。
先ずは、この物価高対策としての消費税減税は必須の政策です。
憲法についても、権力の縛りを強める立憲的改憲の立場の主張をしており、自民党案とは全く異なり、議論の余地はあります。
山形県民の代表として、舟山やすえをもう一度、参議院へ送りましょう。
草島進一
鶴岡、酒田、山形での街頭演説、個人演説会映像です。
ラストスパート 地域まわり 7.9 山形市内
7月9日の最終演説
ダイジェスト版40分
全編
7/5 山形市での必勝 総決起大会 1200名の聴衆に向けて熱弁。
河北町出身 あの石原を打ち負かした東京8区 立憲民主党 吉田はるみ 衆議院議員
安保法案の際の討論で知られる、国民民主党 大塚耕平 参議院議員が駆けつけました。
7/4 酒田市総合文化センターでおこなわれた庄内最終の決起集会 300名
7/1 鶴岡市勤労者会館 鶴岡総決起集会 140名
6/19 鶴岡市第一ホテル 鶴岡集会
7/9マイク納め
舟山やすえ公式youtube チャンネル「教えて やすえちゃん」にもアクセスを。
プロフィール、政策など詳しく知ることができます。
https://www.youtube.com/channel/UCgX_iJmfXY8H8q803NTqWKA
市長の100万円不記載などの件での100条委員会設置への反対討論
年末から年頭にかけての報道などをきっかけに明らかになった、皆川治 鶴岡市長の選挙資金100万円の不記載の件について、議会で市長は12月27日、1月18日の2回の全員協議会で文書とともに説明、質疑応答をおこないました。
文章は以下のものです。
それぞれ、市長の説明に対して質疑がおこなわれました。
その後、「回答には納得でない」「真実をあきらかにしたい」という旨で新政クラブ、公明、無所属の3名によって、100条委員会設置の決議議案が提案されました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1月25日は、その決議案の提案、理由説明、質疑、討論、議決となりました。私は、提案者に次のように質問しました。
●証人喚問が必要と考える際、誰を証人喚問したいと考えているか。
●本当に喚問できるのか。100条が及ぶ範囲は行政事務に係る事となっている、市長や寄付者の証人喚問が地方自治法100条の規定を逸脱し、議会の権限濫用とならない法的根拠はどうなっているのか説明を。
●堺市の市長の場合は、多岐にわたる2億3千万円を越える不記載があって、政治資金規正法違反の容疑で刑事告発されている。その事実解明として選挙資金収支報告書について100条の調査がおこなわれているが、結局は何ら明らかにならなかったと総括されている。その場合「百条委に選挙資金調査権限はない」などの弁護士の見解を元に、市長らは出頭を拒否し、市議会は告発したのだが、大阪地検特捜部は不起訴処分としている。これが先例だ。本当に議会の権限濫用とならないのか。
●パワハラについて、実名での具体的な告発など、訴えはあったのか。。
●怪文書の一つに「パワハラの為、当該職員は極めて厳しい状況に追い詰められ、幹部職員や若手職員の早期退職や休職が相次ぎ、私達が把握されているだけでも一定数の職員がいるようです。」とあるがこの事実実態は調べたのか。以前と比べ、どのくらい増えているのか。
●誰が書いたか分からない怪文書を鵜呑みにして、それを根拠に疑惑として決めつけて調査できるのか
●実名で事実を明確にし、告発がおこなわれているのなら、分かるがこの怪文書2通と実名だけれども具体の事実の訴えでもない文書をうのみにして、100条調査委員会設置なんて、全く考えられない。と思う。
考えようによっては、匿名で怪文書などを創作して、「疑惑だ」と決めつけて、なんでも100条調査委員会を設置できることになってしまう。と思う。大変危険な事だと思う。が、そう思わないのか?伺う。
又、この案件は、実名で具体的に実態を告訴、告発があり、実態があったと判断されて、はじめて議会として動くことができる事だと思う。それもなしに、 怪文書などをうのみにして、事実確認もしないで、あたかも「パワハラがあったかのように疑惑として決めつけ、調査、それも100条委員会をおこなう事は、議会の判断として常軌を逸している。と考える。又、根拠なく疑惑が向けられる方 市長、に対して、名誉毀損にあたるのではないかと感じますがいかがか? 提案者の考え方を伺う。
など、質疑をおこないました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
その後、討論となり、私は、以下、決議案に反対の立場で討論をおこないました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
議会第10号 市長の不記載 100条委員会設置に関する決議につきまして、市民の声鶴岡を代表し、反対の立場から討論を行います。
地方自治法第100条の規定によるいわゆる百条調査権は、その第3項に「六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する」との刑罰が明記されることから判断するに、100条第1項の権限を保持する委員会の設置は地方議会にとって極めて重要な責任が問われる決定であります。
ゆえに、通常の議会、委員会において十分に実効がおさめられない点を補完するときに限定をされる強制権の発動であり、その設置については極めて慎重に行われるべきものであります。
他議会の設置例としては、贈収賄や公金支出の不正、事務や予算の執行に明らかな不正があるなどの事例が認められますが、本件の「選挙資金収支報告の1件のみの不記載、それも訂正済み」に対する調査は、何の究明になるのかよくわからないのであります。
100条調査権は、あくまで行政事務への調査であって、
一部弁護士からは、「選挙資金問題等の調査は、地方自治法第100条の規定を逸脱し、議会の権限濫用であるという指摘があります。
実際にそれを根拠に出頭を拒んだ堺市長のケースがありました。その件に対して議会は告発しましたが不起訴処分となっています。
設置しても、証人喚問が法的に担保されているのかすらわからず、それにより、何を明らかにしたいのか、どうもよく分かりませんでした。
100万円の不記載については。これまでの2回の全員協議会での説明で、支援者からの100万円の寄付の選挙資金収支報告書への不記載があったこと。そして、事実に基づいて2回の収支報告書の修正を行った事。又、寄付を受けた100万円については、選挙資金ではなく自分のお金から返金していること。が明らかになっていると思います。
寄付の不記載については、時効を迎えていますが、違法行為ですのでそれはなんらかの動義的責任を問うことになると考えます。
返却した100万円については、議会で調査しても答えが出せるわけではなく、司法にゆだねるべき問題と考えます。
100条委員会の証人喚問などを行って何を明らかにしようとしているのか。100条設置のの意図、意味は何なのか。よくわかりません。
疑問があれば、更に全員協議会等で問えばいい問題だと考えます。‘
又、寄付をした当人についても、私も先日お伺いし、お話を伺いましたが、先ずは各会派調査し事実確認したらいかがでしょうか。
又、パワハラの項目ですが、実名での具体的な告発などの訴えがあったものでなく、事実確認もおこなわず、こともあろうに2通の誰が書いたかもわからない怪文書と、役所OBの実名入りかもしれないが、具体的事実の訴えとは到底認定できない1文書のみによって、あたかも、「パワハラ」があったかのように「疑惑」を決めつけ、無理やり100条調査の項目にすることは、議会として常軌を逸した暴挙であると考えます。これこそ、極めて慎重に行われるべきものであると考えます。
●100条委員会といえば、以前、4年前になりますが、私と共産党さんとで文化会館問題についての百条委員会の決議案を提案した事がありました。あのときは97億円の行政事務そのものが対象であり、我々が調査対象として議場でも述べた「議決を経ないで改築費増額した件については後に市の第三者調査・検討委員会から「違法」と答申され、不正が指摘された問題でありました。今般100条決議提案の新政クラブさんらによって反対され、廃案となった決議でありましたが、今般提案の決議案と比較すれば実に真っ当な決議案であったと考えます。
今般の100条委員会決議案は、調査に及んだ際、地方自治法第100条の規定を逸脱し、議会の権限濫用と指摘を受ける可能性もあり、さらには、何か特定される疑惑を明らかにしたいという本来の意図よりもただ、マスコミ受けを狙い市長の評判の印象操作のために、只設置したいがための設置のような気がして成りません。新政クラブさんの4年前の討論をそのまま返しますが、政治的パフォーマンスによりマイナスイメージを増幅させることは適当でないと考えます。
議会がそのような意図で、特に数の暴挙によって、ゆがめられてはならないと考えます。
以上、不当、不必要な100条委員会設置について、反対する意思を表明し、反対討論とします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
しかしながら、100条委員会設置の決議案は、賛成多数で可決となり、設置し調査をおおなうこととなりました。
委員構成は以下のとおりです。
佐藤博幸 議員 委員長
加藤鉱一 議員 副委員長
田中宏 議員
石井清則 議員
菅井 巌 議員
富樫正毅 議員
黒井浩之 議員
石塚 慶 議員
佐藤昌哉 議員
五十嵐一彦議員
尾方昌彦 議員
草島進一 議員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2月中には第一回委員会が開催と思われます。弁護士を立て、予算と時間を使っての調査となりますが、質疑、討論などで指摘したように、くれぐれも法の逸脱などのないように注意しつつ議論、調査をおこなっていきたいと考えています。
発端となった記事
山形新聞
鶴岡市長、収支報告書に100万円の寄付記載せず 17年選挙時に受領
2021/12/22 08:10
鶴岡市長の皆川治氏(47)が2017年10月の市長選の告示日翌日、男性支援者から現金100万円の寄付を受け取ったものの、選挙運動費用収支報告書に記載していなかったことが21日、山形新聞の取材で分かった。皆川氏の関係政治団体の政治資金収支報告書にも該当する寄付の記載はなかった。収支報告書の不記載などとして、公選法や政治資金規正法に抵触していた可能性がある。
同日の山形新聞の取材に対し、皆川氏は現金を受け取ったことを認め、収支報告書に記載が必要との認識はあったものの「市長選の忙しさの中で失念していた」と釈明した。今年の夏ごろに記載漏れがあるのではないかとの指摘があったとし「現金は使っていなかったので、返還させていただいた」と語った。
関係者によると、皆川氏は17年10月9日夜、同市藤島地域での個人演説会の後、移動のため車に乗り込んだ際、現金100万円が入った封筒を支援者から受け取った。
支援者はその後、他県での収支報告書の記載漏れに関連する類似事案の報道に触れ、自身の寄付も収支報告書に記載されていなければならないことを認識したという。今年7月ごろ皆川氏に電話し、報告書の訂正を求めた。
一方、皆川氏は寄付を受けてから約4年後の今年8月28日午前7時半ごろ、元県議の男性と共に「返金に来た」と支援者宅を訪問。受け取りを拒まれると、現金の入った封筒を玄関に置いて立ち去ったという。封筒は4年前に支援者が現金を入れたものとは別物だった。支援者は「報告書を訂正すべきで、返金を受けたつもりはない」としている。
政治資金規正法は政治家個人への現金の寄付を禁じているが、選挙運動に関する場合は認められる。公選法に基づき、選挙運動費用収支報告書に記載する必要があり、記載漏れや虚偽の記入は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。今回のケースは既に公訴時効を迎えている。
【皆川治氏の選挙と寄付の経過】
▽2017年10月8日
鶴岡市長選挙告示
▽同9日
支援者が現金100万円を皆川氏に手渡す
▽同15日
皆川氏が初当選
▽2021年3月2日
皆川氏が再選出馬を正式表明
▽同年8月28日
皆川氏が支援者宅を訪問し、100万円を返還する
▽同年10月3日
鶴岡市長選告示
▽同10日
皆川氏が再選を果たす
寄付した支援者、落胆「無かったことにされるのは悔しい」
封筒の頭をはさみで切ると、1万円札がばらばらと出てきた。新券ではなく、上下、裏表の向きもそろっていない。「残念だ」。寄付をした支援者はそう言って肩を落とした。8月下旬、皆川治氏が玄関に置いていったという封筒は開封せず、素手で触れることもなく保管してきた。
他県での政治資金収支報告書の不記載問題に触れ、支援者は今年夏ごろから、報告書の訂正を皆川氏に求めていた。「正々堂々としようと、助け船を出したつもりだったが、返金されるとは思わなかった。市政を良くしてほしいと願っての寄付だったが、無かったことにされるのは悔しい」と語った。
識者指摘「受け取った以上は不記載」
政治資金問題に詳しい上脇博之教授(神戸学院大)は「4年後に返そうと、受け取った以上は不記載で、違法行為であったことは間違いない。個人で100万円を寄付できる人は少なく、こうした寄付を記載しなかったことは重大だ」と指摘している。
憲法を考える。その1。小林節先生
憲法を考える。その1
2022年5月3日に行われた憲法記念日集会での小林節先生の記念講演の動画です。 栃木革新懇様より。
素晴らしい内容です。
「あなたは、どう改憲に向き合うか?」
その1
○自民党案
必要かつ最小源の自衛隊。
→ 必要な自衛のために自衛隊を組織する。
9条のトリック。
○9条、1項 2項に3項書いたら、新しい法が優先し、2項は死文化する。
いつでもアメリカと一緒に戦争に行ける国になっていいんですか?と問いかけるべし。
○憲法9条によって日本は、ロシアのような侵略者にはなりません。自衛権に基づく先鋭自衛隊がいる。ウクライナにもなりません。
その2
その3 質疑応答
○国連憲章の敵国条項(53条1項)がまだ存在しており、日本およびドイツに軍国主義が復帰したら国連メンバーは武力制裁していい。これについては安全保障理事会の承認がいらない。ロシアなどの格好の理由付けになりかねない。
○お花畑といわれたら、日本は9条のおかげで、ロシアのように侵略者にもならないし、ウクライナのようにもなりません。と言いましょう。
○自民党の9条改憲案はトリックです。必要な自衛、海外派兵を合憲化する改悪案です。
その4
○押しつけだろうが、当時の国民は喜んで受け入れた。押しつけと主張するのは戦犯の片割れの被害妄想だ。
○自衛隊は、保安隊、警察予備隊として自衛隊法と防衛省設置法によって設置されている。
R6年度の請願・意見書への草島討論
●R6年度の 請願・意見書(賛成討論をした請願・提案した意見書)
●訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出に関する請願 賛成多数で採択 3月議会
*介護職報酬は月10万円引き上げなどが必要!
●核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書提出に関する請願 賛成少数で不採択(可否同数で議長裁決)R612月
*被団協はノーベル賞受賞なのに残念。
●産業廃棄物焼却処理施設計画(櫛引たらのき台)の見直しをしない限り、県は認可しないことを求める意見書の提出に関する請願。
賛成多数で採択。R612月
*庄内平野の上流の産廃処理施設は危険!
●治安維持法犠牲者に謝罪と賠償をする国家賠償法の制定を求める意見書の提出を請願。 賛成多数で可決 R6 9月 *長年の請願が実現!
●東北電力女川原子力発電所の再稼働を行わない事を求める意見書の提出について 賛成少数で否決。R6 9月