最終日の図。

投票に行こう!
本日、山形県知事選挙の投票日です。
投票日というと、いつも思い出す一件があります。それは、20世紀の終わりにおこなわれた国政選挙での当時の首相の「無党派層には寝ていてほしい」発言です。
ぜひあらためて、以下の当時の朝日新聞の記事をご覧下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
無党派層には「寝ていてほしい」 講演で森首相 朝日新聞。2000年6月20日
森喜朗首相は20日の新潟市内での講演で、有権者の投票態度について「まだ決めていない人が40%ぐらいある。そのまま(選挙に)関心がないといって寝てしまってくれれば、それでいいんですけれども、そうはいかない」と述べた。陣営引き締めのためとみられるが、投票率アップを呼びかける立場の首相が、選挙のカギを握る無党派層などの棄権を期待しているとも受け止められかねない発言だ。
森首相は、新聞各社の情勢調査で自民党が安定多数をうかがう結果となったことについて「新聞が『自民党が強い』と書くと、判官びいきみたいなのもあるし、それじゃあおれたちは逆に(投票を)やってやろうということになる」と警戒感を示した。
この発言について、森首相は同夜、記者団に対し、「寝ていたらいいと言ったわけではなく、よく考えてもらわないといけないという意味だ」と釈明した。
一方、首相の発言に対して民主党の鳩山由紀夫代表は東京都内の記者会見で、「大変さびしい話だ。多くの人に投票所に行ってもらい、雌雄を決するのが、首相の、またすべての候補者の共通の考えでなければいけない。『寝ていてもらいたい』とは何事だと言いたい」と批判した。
http://iij.asahi.com/0620/news/politics20013.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とにかく、今日、民主主義国家、日本の数少ない「権利」のひとつを行使しましょう。
政治を市民のものにするために。
政治をかえよう!
今の政治の最も大きな問題は、真実が権力でねじ曲げられていることだと思う。
僕が最も怒りを感じるところはそこにある。政治、官僚、そして業界の癒着構造によって、真実をおしつぶし、住民をうまく情報操作して操り、事業を進め、実は持続可能な社会に貢献しているとはいいがたい巨大な公共事業やハコモノがつくられてきた。
国政、県政ではこうした公共事業がまさにまかりとおってきたのだと思う。
役にたつ事業であればいい。そして持続可能な地域社会、地域経済に貢献するものであればいい。
しかしながら、その開発行為によって、今まで持続可能な経済を育み続けてきた自然資本や、環境が破壊されるとしたら、どうか。
最悪の場合、こうした議論になると、御用学者によって、真実がねじ曲げられ、そして真実をいうものを議論に参加させない。という構造をつくる。山形県が昨年12月はじめに開いた温泉調査の説明会も、途中で質問を遮っていきなり辞めるという全く説明責任を果たさぬ暴挙に満ちた説明会だった。そしてそれは以前おこなされた流域委員会、流域小委員会、公聴会、すべてにおいて、その理不尽を僕は感じ続けてきた。
おまけに県民を根拠もなく「環境にやさしい穴あきダム」とか、「河床掘削はできない」とか、「偽りの情報」で情報操作し続けてきたのだからさらに始末に終えないと思うのだ。
まさに、全く住民の視点にたたない、そして環境音痴の政治姿勢、そして情報操作やごまかしをし続ける程度の低い河川砂防課の職員たちの姿勢に僕は辟易してきた。
真に住民の側にたち、変革を唱える政治は、こうした矛盾、不条理に挑戦を挑むのだと僕は信じている。長野県の知事時代の田中康夫氏は、少なくともそうした姿勢をもつ数少ない知事だったと思う。次の世代にコンクリートの山を手渡すのではなく、地域ならではのかけがえのない自然を手渡そうと呼びかけていた。
従来の癒着のしがらみでダムをつくるような今の山形県の政治はその姿勢とは真逆といっていいと考える。もう正体はバレている。
その田中康夫さんが、昨年僕らがおこなった11月9日の最上小国川のシンポジウムで次のようなメッセージをくださった。
ぜひ皆さんにお読みいただきたい。
田中康夫 参議院議員からのメッセージ
元祖・脱ダム宣言男 新党日本代表の参議院議員・田中康夫です。
我が舎弟に当たる草島進一さんを始めとする、
最上小国川を愛する皆さんのシンポジウムが、
私の敬愛する今本博健さん、更には矢上雅義さん、天野礼子さんも御参集の中、
開催される事を大変に心強く、嬉しく感じています。
去る10月3日の参議院本会議の代表質問でも述べましたが、
「脱ダム」とは、環境問題に留まりません。
国、県の何れが実施主体のダムも、地元自治体の財政負担は3割近くに上ります。
他方で、ダムに象徴される巨大公共事業は、総事業費の8割近くが、東京や大阪に本社を構えるスーパーゼネコンに支払われます。
詰まり、地元は1割も持ち出し。
巨大公共事業の絡繰りとは実は、
租庸調”の時代の如き、上納・献上システムなのです。ダム建設とは今や、「地方経済」を回復させるどころか逆に疲弊・破綻へと追い込む、河川に染み込む毒薬メタミドホスです。
他方で、日本の国土面積の7割近くを占める森林は荒廃しています。取り分け、その45%は戦後に造林された針葉樹の人工林。広葉樹と異なり、間伐を必要とします。が、驚く勿れ、林野庁の予算の中で森林整備に投じられているのは僅か8%。残り92%は林道建設や谷止工と呼ばれるコンクリートや鋼鉄の杭を沢に打ち込む公共事業なのです。
針葉樹は樹齢45年から60年の間に、「2残1伐列状間伐」と呼ばれる2列残して1列伐採する森林整備を行わねば、幹が太くなりません。昭和30年代に造林された針葉樹の間伐は最早、待ったなしの状態なのです。にも拘らず、間伐が完了しているのは人工林1140万haの約3分の1、400万haに過ぎません。今後6年間は年間55万haを間伐する、と林野庁は計画を発表していますが、それでは6年後も410万haは手付かずの儘です。
実は、間伐に投じる事業費の3分の2は、人件費なのです。即ち、これこそは地域密着型の公共事業。中山間地域の土木建設業従事者にとっての福音でもあります。
故に知事時代、私は森林ニューディールと銘打って、間伐する面積も予算も2.5倍に増やすと共に、森林整備技術を習得する100時限の無料講習会を開催し、地域雇用の促進に努めました。
森林整備の効果は、治山・治水に留まりません。中下流域の農業者にも漁業者にも、更には牡蠣を始めとする河口の漁業者にとっても福音を齎すのです。正に農業・林業・漁業3分野を連携する新“3業革命”です。
とまれ、本日の会合が、御参集の方々のみならず、最早、
「とてつもない日本」改め「とんでもない日本」と化しつつある、我がニッポンを憂う方々にとっての、
新たな一歩を確認し合う時空であります事を、心から願い、メールをお届けします。
脱ダム宣言の田中康夫より。
—————————————————————-
今の政治の問題について、年はじめに動画でメッセージしています。
どうぞごらんください。
http://jp.youtube.com/watch?v=ccJnYVuJhvc&feature=channel_page
また、小国川の問題については、www.ogunigawa.orgでご覧になれます。どうぞご覧ください。
小沢代表。山形入り。
明日、民主党の小沢代表が山形入りするとのこと。
情報をチェックして、ぜひ話を聴きにいきましょう。
アメリカが変わった。日本も変えよう!
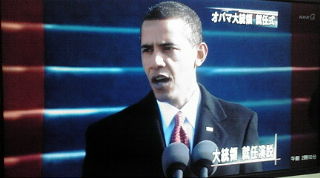
オバマの就任の模様に2人で見入っていた。こんな時代を経験できる幸せを感じたのは僕らだけではないだろう。そして、本当にそろそろ日本も変えねばという気持ちで一杯になってきた。
オバマの演説の一部にこうしたくだりがある。「今日、私たちは恐怖より希望を、対立と不和より目的を共有することを選び、ここに集まった。今日、私たちは、長らく我が国の政治の首を絞めてきた、狭量な不満や口約束、避難や古びた協議を終わらせると宣言する。」「皮肉屋たちは、彼らの足下の地面が動いていることを知らない。つまり、これまで私たちを消耗させてきた陳腐な政争はもはや当てはまらない。私たちが今日、問わなくてはならないことは、政府が大きすぎるか、小さすぎるか、ではなく、それが機能するかどうかだ。」「腐敗と謀略、反対者の抑圧によって権力にしがみついている者たちは、歴史の誤った側にいることに気づくべきだ。」
うむうむと頷きたくなるような現実が、日本の政治にも存在する。
しっかと心に刻み、日本の政権交代のために、一歩一歩やっていくしかない。
オバマに続いて、変革! 信念と行動あるのみだ。
アメリカが変わります。 日本の政治も、まともな政治に、変えましょう!
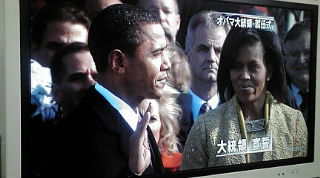
ナチュラルステップジャパンの高見さんと大山、下池をめぐる。

朝、冷え冷えの辻立ちだったが、一緒に立ってくれる人がいるのはなんだかうれしい。エネルギー倍増。
さて、本日は、昨年にホームステイまでさせていただいたスウェーデン在住の、ナチュラルステップジャパン 代表、高見幸子さんが鶴岡にいらして、黄金保育園の雪の野外教育を視察された。同じくムッレ教室を新潟や、東京で中心的に運営されている下条先生や阿部先生もいらっしゃり、今の保育の課題などについて有意義な意見交換をすることができた。
自治体運営の保育園と民間保育園の保育士の給料格差、また、子供一人あたりの先生の数などなど。3歳児に対して日本だと20人に一人ということになっているがスウェーデンだと15人に3人。つまり5人を一人で看ることが法律で義務付けられているとのこと。
こうした違いが、野外保育などをできにくくしている背景だとみなさんおっしゃっておられた。
雇用形態として、日本の保育士、そして介護士の給料体系があまりに低すぎるとよくいわれている。
これは社会のシステムの問題だ。とても持続可能なシステム構築になっていないのだ。
その後、4名で大山下池へ。日暮れは5時半。日暮れ近くにオオヒシクイの群れ、その前に白鳥、そしてその日は、真っ暗になる直前に、一挙に飛び立ち、弾丸のように飛び去っていく鴨の群れを観察できた。
さすがは、野外保育、野外教育の専門家の先生方。 大山下池、すばらしい!の連続だった。
ありがとうございました。
さて、本日は、深夜1時からオバマの就任演説。米国が変わる瞬間。みんなでしっかと見ましょうね。
鶴岡型 小水力発電 稼動! 鶴岡高専 オープンクロスフロー 水車

今まで水力発電というとすぐにダムなど大規模なものばかりとおもいきや、実は、水車を水路につくれば、簡単に電気は起こせる。でも、その形状によっては、ごみがひっかかったり、なかなかメンテナンスがめんどうだったり諸々課題があるようだ。
高専の丹先生、本橋先生らが開発していたのが、そうした課題を克服する形状をもつオープンクロスフロー型の水車。今回下水処理水を活用してこの水車の実験がはじまった。大体、3kwの出力。一般家庭8件分の電力をまかなうことができるとのこと。
この設置については、水利権や河川管理の関係で国土交通省の許可がなかなかでなくて設置するのにずいぶんの時間がかかったようだ。
諸々の困難を乗り越えて実現した、実験の開始に拍手を送りたい。
鶴岡の中山間地、扇状地の水路を使って、こうした水車をまわせたら、結構な電力がとれるのではないか。そばで見ていて、風力よりも安定しているし、大きな可能性を感じた。
グリーンニューディールが叫ばれる今、こうした研究こそ重要視すべきだ。
今後の展開に期待したいし、こうした利用における水利権の壁の問題について、熟考しなければならない。
寒だらまつり。天気良くて最高でしたね。

朝10時すぎに鶴岡駅着。家にもどるとすぐに寒だら祭り。天気はぽかぽか。旗もって呼びかける。この4年、農業予算が秋田や青森の半分になってしまった山形県。これじゃ、こんなおいしい食の文化が守れない。おいしい寒だらまつりのためにも、、、と呼びかけると、結構ガッツポーズをいただきました。
皆さん、お疲れ様でした。近年で最高の人出でしたね。
その後、6小コミセンの新年会。諸々ご意見をいただいた皆さん、ありがとうございました。
神戸で14年前の自分に出会う。

神戸。2005年にフォーラム開催にいってから、4年ぶりの神戸。当時の同士たちと再会し、1.17 5時46分。東遊園地の祈りの会場で黙祷す。6国道2号線沿い、灘と東灘の中間にある御影公会堂、石屋川公園に立つ。そして、人と防災センターに行き、「神戸元気村の活動」という表示と、当時、夢中でシャッターを切った1万点からピックアップされた、当時の数点の写真。「元気村の3キログラムのお米に励まされる」という表示、そして、そのとなりにあった手記の中で自分の名前を発見。
当時。がれきの中で「笑顔をとにかく一つつくること」をミッションに。多種多様な知恵と行動力を活かし、0から1をつくる。そんな「今」という瞬間が連続していた。僕は眠るのを忘れて、被災地とその外をつなぐ、電話をかけまくっていた。1000人規模の炊き出し、がれきの中で畳7畳のステージをつくってやったコンサート。などなど、次々に変わるニーズを読んで、バウさんと一緒に、当初の3週間ぐらいに約30以上ものプロジェクトを抱え、実行していった。炊き出しを食べ、150日のテント暮らしをしながら、徹底的に打ち込んだあの日々は僕の細胞のどこかに刻みつけられている。その後、重油災害、新潟水害、中越地震、中越沖地震、、、、。
災害救援も、水問題も、ダム問題も、そして議会活動の中で取材をしたり、文書を練り上げていくときも、取り組むときの思いは変わらない。
あれから14年になる。神戸の犠牲を今の社会はどれだけ活かせているだろうか。そして、僕自身は、神戸から学んだものを、どれだけやれているだろうか。と問われる1日だ。
さて、2009年も一歩、「神戸」の6000人越える 犠牲を活かすためにも、そして、あのとき生み出した 「ボランティア元年」という新しい文化を、活かすためにも、
「動けば変わる。信念と行動の年にしたい。
当時の神戸元気村の記録:http://homepage.mac.com/stern8/iMovieTheater29.html
元気村代表のバウさんの「生きる」で描かれた当時の元気村の一幕
http://www.peace2001.org/2006/main/bow/20080911_bow_01.html











