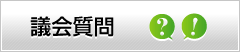小国川問題 最上小国川流域環境保全協議会 会長へアユ研究者が意見書提出
本日8月1日、最上小国川の清流を守る会 共同代表 高桑順一氏、NACS-J自然保護協会 評議員 出羽三山を守る会 佐久間憲章氏 山形県議 草島 の3名で、最上小国川保全協議会の調査内容について、アユ研究者による意見書を最上小国川流域環境保全協議会 会長である原慶明氏に午前10時にメール提出。また午後3時に山形県県土整備部 河川課へ提出しました。その後、県庁記者室で記者会見をおこないました。
提出したのは以下のものです。
アユ研究55年の日本の第一人者、川那部浩哉先生を筆頭に、実際に流水型ダムの先例である益田川ダムの影響調査をしている竹門康弘先生、5月のシンポジウムで益田川程度の低濁度の濁りで実際の河川で漁獲高が大幅に減少した事例を発表してくださった朝日田 卓先生、「ここまでわかった鮎の本」http://hito-ayu.net/index.html などで知られる高橋勇夫先生が、1ヶ月半を費やして調査データを検証して協議していただいた結論です。
これは絶対に無視できない 「科学的な論証」であります。
最上小国川流域環境保全協議会
会長 原 慶明 殿
「第12回最上小国川流域環境保全協議会資料(2013年11月21日 山形県)」のうち、
アユを中心とする調査内容に関する意見書 (要約版)
川那部 浩哉(京都大学名誉教授)
竹門 康弘(京都大学防災研究所准教授)
朝日田 卓(北里大学海洋生命科学部教授)
高橋 勇夫(たかはし河川生物調査事務所代表)
1. 意見書提出のいきさつ
2014年5月27日、最上小国川流域環境保全協議会会長原慶明さんは、山形県議草島進一さんの質問に対し、「最上小国川環境影響調査委員会の検討内容に欠けているファクターは何なのかを教えて欲しい」と述べた。草島さんは、「第12回 最上小国川流域環境保全協議会 資料」(以下、資料と呼ぶ)を6月12日に上記4名に送り、とくにそのうちの47~92ページについて、「意見が欲しい」と要請した。
この意見書は、この依頼を受けた4名が当該資料を検討し、それに対する意見を整理したものの要約版である。
2. 第12回 最上小国川流域環境保全協議会資料の問題点
1) 調査の目的や方法が吟味されていない
個々の調査項目について具体的な目的がどこにあるのか明白ではなく、また想定される目的に対して調査方法が相応しいかどうかがほとんど吟味されていないと判断せざるを得ない。
具体例 「水産的重要種」であるアユの餌であるとする付着藻類や細菌については、種組成・細胞数・乾燥重量・クロロフィルa量・強熱減量などをばらばらに調べたのみで、同時に調査したアユの「はみあと率」との関連性がまったく検討されていない。しかも細胞数以外の項目はダムの影響を検討する材料としては一切使われていない。また、「堆積砂の挙動調査」や「洪水時の剥離」に関する検討過程においても、河床型や礫径によって相違する可能性が考慮されていない。
2) 限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている
調査そのものは限定的な条件下で行われているにもかかわらず、そのことを無視して、結論が導き出されている。
具体例 付着藻類は一貫して拳大の石礫から採取されているが、このような小さな石は小規模な洪水でも藻類の剥離が起きやすい。したがって、付着藻類調査は「藻類が剥離しやすい状況にあった小さめの石礫を選択的に採取して、その剥離状況を調べた」ことになる。このような方法に基づいて行われた付着藻類調査から言えることは限定的であり、この分析結果から、「50m3/s 程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」という考察を導き出すことは非科学的である。さらに、それを根拠とした「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる」という結論も導き出すことはできない。
3) 各調査に結びつきがない
調査がそれぞれ「ばらばら」に行われているうえに、それらを複合的・総体的に結びつけようとせず、言わば「単純な足し算」によって「考察」され、「結論」なるものが導かれている。
具体例 「各調査地点の河床状態はアユ漁場として良好な状態にあると推察される」とまとめられているが、アユの多さを表現する「はみあと率」は地点によってかなりの差がある。アユの漁場として評価するのであれば、河床状態調査、はみあと率ならびに付着藻類調査の時期や地点を合わせておくことが不可欠であるが、それすら行われていない。
4) アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない
アユに対する影響を検討するものであるにもかかわらず、アユそのものに関する調査・検討は何一つ行われていない。仮に「餌環境への影響は軽微である」ということが事実であるとしても、アユの棲息が充分に成立するためには、他のさまざまな環境条件が必須であるが、それらの検討が全くされていない。アユの実際の分布からは「アユ漁場として良好な状態にある」というような単純な結論を導くことはできない。
3. 最上小国川流域環境保全協議会への提言(今後の調査に向けて)
小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて、アユの餌環境やサクラマスの産卵環境の悪化が懸念される(サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲で発見されている)。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。
上記のようなピークカット率の高い流水型ダムによって高い確率で起こると予想される影響に関しては、これまで全く調査されておらず、全く検討もされていない。したがって、今後これらの項目について詳細な調査を行い、影響をつぶさに検討することが必須である。
一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれに基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを強く要請する。
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
詳細版
最上小国川流域環境保全協議会
会長 原 慶明 殿
「第12回最上小国川流域環境保全協議会資料(2013年11月21日 山形県)」のうち、
アユを中心とする調査内容に関する意見書 (詳細版)
川那部 浩哉(京都大学名誉教授)
竹門 康弘(京都大学防災研究所准教授)
朝日田 卓(北里大学海洋生命科学部教授)
高橋 勇夫(たかはし河川生物調査事務所代表)
1. 意見書提出のいきさつ
2014年5月27日、最上小国川流域環境保全協議会会長である原慶明さん(山形大学名誉教授)は「アユの餌環境 流水ダム」という演題で公開講演を行った。講演後における草島進一さん(山形県議会議員)との質疑の中で、原会長は「最上小国川環境影響調査委員会が出した調査において、欠けているファクターは何なのかを教えて欲しい」と述べた*1。そのために草島さんは、「第12回 最上小国川流域環境保全協議会 資料」*2(以下、資料と呼ぶ)を6月12日に上記4名に送り、とくにそのうちの47~92ページについて、「意見が欲しい」と要請された。
この意見書は、草島さんから依頼を受けた4名が当該資料を検討し、それに対する意見を整理したものである。
2. 第12回 最上小国川流域環境保全協議会資料の内容に関して
2-1) 付着藻類調査(資料47-52p)に関して
この調査の「目的」がそもそも何なのかが、これでは判然としない。また「調査方法」においても、「早瀬」・「平瀬」とのみあるだけで、その具体的場所も状況も記載されていない。しかしながら、「付着藻類」の質や量がごく狭い場所でも互いに異なることは、広く知られている事実である。また、1箇所において何個の標本を採取したかも記載されていない。疑って言えば、各1標本であった可能性が高く、それでは生態的調査としては、ほとんど意味のないことも周知の事実である。また、2013年は僅かに1回の調査であり、他の年についても調査日は各年2~5回程度で、しかもその日は「任意」に選ばれているように見える。アユの棲息環境の状態を、後に書かれているようにダムなどとの関係において把握したいのであれば、少なくとも増水・洪水・渇水とその継続時間などを考慮して、その都度連続して調査を行い、その結果を明らかにする必要がある。
さらに細かいことに言及すれば、例えば52pの表において、その時期の各最多優占種の比率のみを示す意味は明らかではない。また「全細胞数に対する優占種の割合」との文言からすれば、これは細胞数における百分率と想像されるが、生物量などでの検討も必要であろう。さらに、「6月~9月頃は、藍藻類のHomoeothrix属藻類が優占し、それ以降は珪藻が優占する傾向がある」と結論づけているが、これは表からは素直には導きがたい。アユの摂食によって珪藻類の比率が減少し、藍細菌類の比率が増加することは、近年知られるようになっているから、そのようなことを何らかの意味で導きたいのであれば、藍細菌と珪藻との比率をむしろ示すべきであったろう。また「はみあと率」なるものも、当該石の表面のはみあとの数なども記されておらず、この場合においても、科学的調査における方法記載にはなっていない。
この調査が、最終的にはアユへの影響を判断するために行われたものであれば、アユの多さの目安となる「はみあと率」とアユの主餌料である付着藻類の各分析項目との関連性がまったく検討されていないのはなぜか。そのような基本的な分析さえ行わず、最終的な結論を「アユの採餌環境に対するダムの影響はほとんどないものと考えられる(92p)」とすることは、危険このうえもないことである。
2−2) 河床状態調査(資料53-57p)に関して
調査は2013年11月の1回だけのようで、また場所の詳しい記載もなく、それらの問題点は先に記したものと同様である。ついでに記せば、この場所は先の藻類調査の場所とも異なっていて、互いに「独立」に選ばれたものと受け取れる。方法も明白には書かれていないが、文章と図から判読してみると、底に重なっている石のうちいちばん表面のものだけについて、はまり石・浮き石を判別し、その下にあるものについては考慮していないように受け取れる。しかし、出水・洪水の折りはもちろんのこと平水時においても、底の石や砂礫が動くのは周知の事実であり、それは石の重なり状態を含め底質の状態によって大いに異なるものだ。アユの棲息環境として、「付着藻類」の状況を把握したいのであれば、このような配慮のもとでの調査が必須である。なお、「上流域2地点では、(中略)下流域(3地点か?)と比較して石の大きさは小さい傾向が見られた」とあるのは、資料53pの地図を瞥見する限り、その両地域の流程地形からみて当然と推測される。ここでも先に指摘したように、「地点」の中の個々の調査点の詳しい記載がなければ意味のないことは、ここからも明らかである。
「各調査地点の河床状態はアユ漁場として良好な状態にあると推察される」とまとめられているが(資料p57)、アユの多さを表現する「はみあと率」は地点によってかなりの差が生じており、アユの実際の分布からは「アユ漁場として良好な状態にある」というような単純な結論は導けない。基本的なことであるが、アユの漁場として評価するのであれば、河床状態調査とはみあと率や付着藻類関連の調査は時期や地点を合わせておくべきで、そうすれば、アユの生息環境をもう少し体系的に評価できたと考えられる。このように、本調査はきわめて断片的で、これが意図的でないとすれば、最上小国川流域環境保全協議会においては調査計画そのものが十分に審議されてこなかったと判断されてもしかたがないと考えられる。
2−3) 「付着藻類の影響検討について(資料58-92p)」に関して
2-3−1) 剥離(資料60-63p)に関して
資料では、ダムサイト地点での流量が55・54・24・20・18・8m3/ secであった6洪水の後に総細胞数などを調査し、洪水以前のそれと比較した結果が示され、「50m3/s程度で、末沢川合流点から下白川橋まで、付着藻類層細胞数が3%以下となっていた」としている。そして、「ダム地点で50m3/s程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」とまとめられている(資料61p)。さらに、「影響評価」に関する結論は、「3年に1回程度以上の洪水ではダムあり・なしに係わらず、付着藻類はほとんど剥離すると考えられる。2年に1回程度以下の洪水では、ダムあり・なしで流量変化が小さいため、付着藻類はダムなしの場合と同様の状況を維持すると考えられる。 → 付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる」となっている。
洪水前後の総細胞数の表(資料60p)では、確かに50m3/ sec以上の流量を示した2回の洪水においては、4地点ともに0-3%の残存率になっている。それに対して例えば下白川橋での残存率は、20-25m3/ secの流量の場合でも3-9%に過ぎず、8m3/ secの流量の場合でも29-57%の残存率となっている。さらに言えば、残存率「51%~」としてまとめられている「総細胞数残存率」の実際の数字を表から拾ってみると、871%,337%,257%,215%,219%,59%,57%と非常に幅広く、これが意味するところを考えれば、ここで言う「残存率」なるものはほとんど、いや全く意味が無いものである。とにかく、「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる(資料63p)」という結論は、これらの調査結果からは全く出てこないと判定できる。
付着藻類の採取は、調査初期から一貫して「拳大の石礫にコドラートを当てて、ブラシではぎ取る」というやり方で行われている(調査状況写真を見ると実際には採取した石礫は拳大~径20cm程度であり、実のところはあまり一貫性もない)。藻類の剥離は礫の大きさ(洪水による動き易さ)に大きく影響を受け、一般的にいえば、小さい礫ほど藻類が剥離しやすい傾向にある。小国川の河床材料のほぼすべてが「拳大の石礫」構成されているわけではもちろんなく、他の調査状況写真を見ると小国川の河床には採取した石礫よりも大きな石はごく普通に観察されるし、河床材料調査(資料53-57p)においても、「径25cm以上が多く、アユの生息に好適」と結論づけられている。したがって、付着藻類調査は「藻類が剥離しやすい状況にあった小さめの石礫を選択的に採取して、その剥離状況を調べた」と受け取られても、弁明することの困難な状態になっている。したがって、このような方法に基づいて行われた付着藻類調査から言えることはほとんどなく、この分析結果から、「50m3/s 程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」という考察(資料61p)は、完全に非科学的である。さらに、それを根拠とした「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる(資料63p)」という結論も導き出すことはできない。
2-3−2) 生育基盤(資料64-87p)」に関して
①洪水時の河床材料の変化
資料では、洪水時の河床材料の変化を洪水の大きさ別に予測し、「付着藻類の生育に対する影響は小さい(資料87p)」ことの根拠としているが、検討に用いられたデータはシミュレーション等により得られたもので、他の流水型ダムにおける調査結果に基づくものではない。もしシミュレーションや実験結果を用いるならば、その条件設定が妥当なものであることを科学的に証明しなければならない。さらに「影響が少ない」とするなら、その程度がどれくらいなのかを予想される魚類資源の減少率等の具体的数値で示す必要がある。
資料では、洪水時の河床材料の変化を洪水の大きさ別に予測し、いずれのケースでも短期間で洪水前の状態に戻る、または変化がないとされている。しかし、同じ流水型ダムである益田川ダム(2005年竣工)では径100mm以上の礫がダム上流(貯水池内)にすでに堆積しており、定期的に礫をダム下流へ人為的に移動することが検討されている(2014年5月26日 京都大学防災研究所角哲也教授 最上町での講演*3)。このような既設の流水型ダムにおける土砂の堆積状況から考えると、このシミュレーションの妥当性には大きな疑問がある。
②平水時における堆積砂の挙動調査に関して
平水時の砂の挙動に関する現地実験の場所として選択された「平瀬」とは通常、「浮き石」が少なく、表面の比較的平らな「はまり石」が主になっている場所を言う。そのような場所を「堰き止め」、一様な「4号珪砂」だけを沈下させての測定は、著しく流下し易い条件での実験結果に過ぎず、この川の通常状態を再現したものとは言えない。野外での充分な観察に基づいて実験を行わなければならないことは、生態学のごく初歩の常識であるが、それは全く満足されていない。
砂の挙動に関する現地実験では、平瀬が「アユの主な採餌場」とされ、そこでの野外実験の結果から、「仮に砂が過剰に供給されたとしても、アユが採餌する面はほとんど被覆されず、日常的な流量で流下することから、付着藻類の生育に対する影響は小さい」としている(資料87p)。しかし、小国川において平瀬がアユの主な採餌場となっているということの根拠は示されていない。一般的にアユの生息場所は瀬だけでなくトロ、淵まで様々な河床型に及び、それぞれの生息場で摂餌(採餌)行動が行われている。小国川でも実際にそれぞれの河床型がなわばりアユ(一定の場所に定着した個体)を釣る友釣りの漁場となっている。環境影響調査委員会が行った実験は比較的流速の速い(影響の出にくい)平瀬のみで行われており(資料70-83p)、なぜ、より影響が強く出ると予想される淵やトロでの実験も行なったうえで影響を判定しなかったのか理由が分からない(平瀬を選んだ根拠はアユの主な採餌場ということらしいが、それは事実と反する)し、現在の検討結果は正しいものかどうかさえ疑わしい。また、この実験の組み方では「影響が出ないようにセットされた」と言われても致し方ないのではないだろうか。
③「河床形状」について
方法も結果も、少なくともこの「資料」内ではほとんど示されておらず、論評することもできない。しかしながら、87pの影響評価では「ダムあり・なしでの河床形状の差異は小さいと考えられる ⇒ 「瀬や淵の減少・拡大等の河床形状の変化による影響は小さい」と考えられる」となっている。しかし、これを導いた「根拠」を見つけることは、まことに残念ながらできなかった。
そもそもダム堤体建設予定地から下流の流程は、河床材料変化の数値計算で条件としたような一様の河床ではなく、各所に岩盤が露出した河床であることから、環境変化の実態を把握するにはほとんど役に立たないと考えられる。さらに、小国川で計画されているダムは、既存の流水型ダムに比べてピークカット率(洪水調節率)が高いことから、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥だけが流出することが予測される。したがって、ダム下流の河床形状への影響を評価するためには、このような仮説に基づいて、現場の河床地形の境界条件を加味した予測をやり直す必要がある。
2-3−3) 結論(資料92p)」に関して
ダムの影響は、「①付着藻類へのダムの影響はほとんどないものと考えられる。②「特に、アユが主に採餌する平瀬の巨礫上面の付着藻類に対する影響は小さく、アユの採餌環境に対するダムの影響はほとんどないものと考えられる。」と結論づけられた
繰り返しになるがこの結論は、それまでに提示された結果の分析からは、全く導き出せないものと考えられ、これへ導く「理屈」もまた、ほとんど示されていない。
2-3−4) 資料に書かれている内容に対する一般的意見
「付着藻類調査」や「河床状態調査」は、その場所や方法が明白に記載されておらず、また調査結果もその信頼性が確認できない状況にあり、いや、個々の調査に関する具体的な目的がどこにあるのかも明白でなく、またその目的を調査するに相応しいかどうかすら、ほとんど吟味されていないと、残念ながら判断せざるを得ない。すなわち、30年以上前にコンサルタント会社が、全くの<ルーティン=ワーク>としてやり、全面的な批判にさらされて撤回した「調査」を、彷彿とさせるものと言って良いのではあるまいか。
他の「重要な生きもの」の扱いについてはここでは言及しないが、少なくとも「水産的重要種」であるとして取り扱ったかに思われるアユについても、その餌であるとする付着藻類や細菌についての、種組成・細胞数・乾燥重量・クロロフィルa量・強熱減量などだけで、しかも後の3項目は考察材料としては一切使われていない。
また、「河床状態調査」なるものは、「アユの漁場として良好であるかを河川環境の面から評価するための基礎資料」とされているが、アユが棲息・利用する「河床型」をすべて調べているわけでもない。さらに、洪水による「剥離」や「堆積砂の挙動調査」においても、「河床型」により相違する可能性すら考慮されておらず、また先に記したように、いかなる目的に対しての実験なのか、少なくとも「明白」ではない。
ダムの設置によって、それより下流の河床形態が大きく変化することは、すでに良く知られている。「流水型ダム」であっても、大きい岩や石はダムで一旦貯留されるものであり、もしもそれすらがダムを「通過」するとすれば、治水のためのダムを作る「意義」や「理由」はないことになる。果たしてしからば、砂礫の一部は通過してその下流部に堆積するにしても、大型の岩や石は上流からは補給されず、ダムの下流部においては、流出だけが生じることは、ほとんどすべてのダムで現実に見られている現象である。それが、アユの餌となる「付着藻類」に大きい影響を及ぼさないものかどうか、少し想像するだけでも明白である。
ついでに付け加えれば、例えば、出水・洪水前後の「付着藻類」の調査、「河床状態」の調査、さらには「剥離」・「生育基盤」・「濁り」の解析などは、他の地域にある既存の「流水型ダム」の上・下流において行うことによってこそ、ある程度意味のあるものとなる。そのような河川における調査が今回の「資料」において皆無であることは、極めて不思議であり、かつ異例のことと考えられる。このような既存の河川における様態は、もちろんそのままでこの小国川に当てはめられるものではないが、それを参考にした考察の無いのは、極めて不自然なことである。
2-3−5) この「資料」のさらに致命的な欠陥
この調査は、すでに各個所で指摘してきたように、ほとんどすべての内容において大きい問題があり、またその「結論」なるものは、これらの「調査結果」から「科学的に導かれた」ものとは到底言えない。
しかし、それにも増してこれが致命的と判断できる理由は、調査がそれぞれ「ばらばら」に行われているうえに、それらを複合的・総体的に結びつけようとせず、言わば「単純な足し算」によって作られているところにある。いわゆる「環境問題」が、個々の科学分野から科学哲学に至るまでの広い範囲に深刻な反省をもたらしてきたことは、すでに周知の事実であるが、この「資料」の中にこのような視点を見つけることは出来なかった。
さらに不思議極まりないのは、アユの棲息に及ぼす影響調査として、アユの通常時の餌である石面付着生藻類・細菌の問題だけが採り上げられ、アユそのものに関する調査・検討が全く行われていないことである。仮に、アユの餌に関して「影響が少ない」としても、それだけで「アユに関して問題がない」、あるいは「軽微である」と判断することは、単純な理屈のうえから言っても、あり得ないことである。
また当面の「環境改変」のことで考えるならば、その結果として、どのような影響がいわゆる「生態系」に生じるかについては、考えられるあらゆることを考察し、しかも「影響がある」と想定してみることが大切である。これは周知の通り、近代統計学に言う「帰無仮説」の原理でもある。
極めて単純な事例を挙げれば、ダムにおける「魚道」の問題がある。ほぼ40年ぐらい前まで、いや、あるいは30年前であってもまだ、「魚道の遡上率」とは、魚道のもっとも下の「ます」に入った魚が、いちばん上の「ます」に入る比率を示すものと、誤って理解されていた。しかしながら、その値が仮に100%に近いものであっても、下流から遡上してきた魚が、その魚道のいちばん下の「ます」を発見する比率とそれを捜すのに要する時間の問題、魚道を通過した後にそのダムの湛水域を通過するあいだに起きる障害、例えばどれほどの長時間を要するかの問題、などなどを考慮する必要があり、魚道遡上の「達成率」とは、魚道の無い状態の場合と比較しなければ正しいものにはならない。また、魚道の周辺には魚食性の鳥類などが集って来るのが通常で、魚道の遡上に「辛苦している」魚を捕食する量がかなり大きいことは周知の事実であり、また湛水域における摂食あるいは捕食の増減の問題も、計算に入れなければならない。こうなると、魚道の達成率は、かなりの程度に低いものにならざるを得ないのであり、そのことは今ではかなり広く知られているところである。
今回の小国川「ダム問題」に関係して一つだけ触れるならば、その「流水型ダム」の「穴」の部分は、何回かの出水ないし洪水によって、どのような状態になると、この「資料」の作成者は予測したのであろうか。大型の岩・石のほか材などの蓄積は、少なくとも「ある程度」は起こるに相違ない。それをもし「人為的に取り除く」とするならば、その方法等についての「具体的提案」が少なくともなされ、またそれによる効果が慎重に検討されなければならない。また、それらの物体の蓄積状態において、アユなどの魚はその場所を自由に、すなわちこのダムの存在しない状態と同様に、遡上・降下できるかどうか、これらは考察の対象にしなければならない筈である。両側回遊魚以外の「純淡水魚」もまた、それぞれの生活史に応じて、川を遡上・降下することは、これまた今や周知の事実であるから、アユなどだけでなくそれらの魚に対する影響も、同じく考察の対象にする必要がある。
そもそも、まだ人智には限りがあり、あらゆる可能性を考えようとしても、多くの場合考慮の対象に拾い上げることの出来ない影響は、質量ともに極めて大きいものである。とくに「環境改変」問題においては、従来のほとんど全ての事例において、事前予測を越えた問題が結果として生じてしまっていることを、充分に認識しなければならない。
その点では、「影響は小さいものと考えられる」とか、「影響はほとんどないものと考えられる」などと記すことは、重大な誤りになる可能性がたいへん大きく、いや、それ自体が重大な誤りであり、また事後になって、「この程度の影響は<小さいと>と言った範囲である」とか「<ほとんどない>の範囲である」とかと、「責任回避」の重大な要因になってしまったのが、現在までの一般的な「姿」であり、また今後もその可能性が極めて高い。
したがって「生態系」ないし環境への影響評価は、ありとあらゆる「想定される事象」を複合的・総体的に考えたうえで、せめて「いくら大きく見積もっても、xx程度である」というように、結論づけなければならない。「想定外」などとの「ことば」を今後は使うことのないよう、特に気をつける必要がある。
3. 最上小国川流域環境保全協議会への提言(今後の調査に向けて)
最上小国川流域環境保全協議会第2回中間とりまとめ 平成26年5月」において「④動植物重要種および魚類(アユ等)の採餌環境については、(中略)環境保全協議会で審議した方針に基づき、継続して調査を行っていくことが必要である」と書かれている。この文章の意味するところは「明晰判明」とはとても言えるものではないが、アユに関してだけ言っても、アユそのものに対する影響の研究を含め、少なくとも「資料」で見られたような「環境保全協議会で審議した方針」を全面的に越えて、優れた調査とそれに基づく科学的な考察・論議がぜひとも必要である。
小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて,アユの餌環境やサクラマスの産卵環境の悪化が懸念される(サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲で発見されている)。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。また、わずかな濁水でも大きな影響を与えることは、岩手県の早池峰ダムの調査結果などから明らかとなっており(流水型ダムとは条件が異なるものの、2-6 mg/Lでも大きく影響し、アユやウグイの漁獲量が1/5以下に激減)、最上小国川で施工中の仮設備(トンネル)工事で行っている濁水処理レベル(3 mg/L)でも影響が出る可能性がある。また、いくつかの砂防堰堤(岩手県中井砂防堰堤、神楽砂防堰堤等)で報告されているような、堆積物の大量流出による下流域の魚類生息環境悪化も懸念される。
流水型ダムが建設された場合の付着藻類への影響に関して、最上小国川環境影響調査委員会において「アユの採餌環境に影響なし」と結論づけた。しかし、長期的にみると、ダムによるピークカットのために河床の攪拌頻度・強度が低下し、大型糸状緑藻や蘚苔類が河床を覆うようになる可能性が高く、その場合にはアユの餌場そのものが失われ、「アユの採餌環境に悪影響が出る」可能性は極めて高い。また、大型糸状緑藻や蘚苔類が河床に繁茂しやすくなると、アユの生息場そのものの消失につながる。実際、大型糸状緑藻の繁茂は全国各地のダムのある(つまり河床の攪拌頻度・強度が低下した)河川で普通に見られ、漁業に大きな悪影響が出ている。このようなピークカットによる河床の攪拌頻度・強度が低下することで起こりうるアユおよびアユ漁への影響に関しては、まったく検討されておらず、今後の調査に組み込むとともに、アユおよびアユ漁への影響について慎重に検討することが必要である。
ヤマメ・サクラマスの集結する大きな産卵場がダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲でも発見された。小国川全域が国の準絶滅危惧種に指定されたサクラマスの産卵床である。しかし、それらの産卵床は、河床に卓越する岩盤の上に堆積した石礫や砂利によって形成されているのが現状である。したがって、小国川ダムによる土砂供給様式の変化は、とおり一辺の一次元河床変動計算ではなく、現場の境界条件に基づいたきめ細かい予測計算によって影響の評価をし直す必要がある。
以上のように、ピークカット率が高い小国川ダムでは、洪水攪乱規模の減少を通じて、下流河川の生態環境は確実に変化すると考えられる。その結果、ヤマメ・サクラマスの産卵床やアユの生息環境への影響や、鮎の品質を低下させる可能性は否定できない。長期的な観点から経済損失を検討し、事業計画の経済効果の計算に組み入れることが必要である。
一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれに基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを強く要請する。
以上